
 |
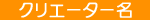 |
りや |
 |
主にファンタジーや現代モノを書いております、
りやと申します。どうぞ宜しくお願い致します。
シリアスやダーク、また、ほのぼのと甘い傾向が強めです。
反対にギャグ(特に恋愛に依存しない形)は苦手としております。
恋愛要素に関しては女性から男性への女性視点が得意で、
逆に女性が複数の男性に好かれるシチュエーションは
不得意になります。女性向け(男×男)はどんとこいです。
ひたすら言葉のリズムと情緒ある作品に命を懸けてます。 |
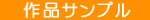 |
■サンプル1
艶を持たない紺色の瓦、それから零れていく雨粒が窓の向こうで、薄い霧の幕を落としていた。しかし数が多く、また数時間という長期戦が続いている状況からそれは厄介なものへと成り果て、街路を通り過ぎようとする人足をまばらにさせる。建物の何処かしらを叩く音が小さいからか、少し幻想的な光景ではあったが、自分たちにとっては迷惑に変わりなかった。そんな外の世界に視線を投げながら、彼は小さく溜め息を吐く。
歳は多く見積もったとしても十代後半。髪の色に肌にまとう服装と、全体的なモノトーンのなかで青い瞳が、強烈な印象を放っていた。幼さはまだ色濃く残るが、その双眸には確かな意志を感じられる。平凡と称されるような人生を送ったなら、歳を経た人間でも身につかないほどの。
「どうかしたか? さっきからぼーっとしてっけど」
投げかけられた声を聞いて、彼は伏せていた顔を横へ向けた。うなじに少し触れる黒髪が、くすぐったい。一度開きかけた唇を声無きまま塞ぎ、ほとんど同じ高さにある相手の顔を見返した。
声を掛けてきた男は、背丈こそ同じでも彼より体格がいい。華奢に見えがちな身体つきがコンプレックスの彼には、男の腕力が自分よりも更に鍛え抜かれたものだと知っている。知っているからこそ、羨ましいと思うのかもしれないが。
黒髪と蒼紫色の髪、その髪質も細くすっとしたストレートに寝癖と格闘しそうな剛毛と随分違う。中性的で穏やかな雰囲気の彼と、兄貴分な性格を窺わせるはつらつとした笑みの男。明らかに血の繋がりはなかったが、それでも何かしら共通するものがある、そう思わせる雰囲気を互いに放っていた。
「…いや、何でもないよ」
言って笑い返してみせると、男はそうか、とだけ返して視線を窓の外へ向けた。実のところ、彼も男も景色なんて見ていないのだろう。心は遠くへ、けれども届かない。彼は胸の奥に詰まる記憶をまた溜め息に化かせた。
(あのときもこんな天気だったよな、ミオーレ…)
自嘲的に胸中で呟いて、密かに拳を握った。瞳を閉じて視覚を遮断すれば、聞こえるあの音。それから手に触れたあの感触。…そして、視界に映っていたあの赤がよみがえる。
中途半端に降り続く雨だった。鬱陶しいとは言えないが、心地良いわけでもない。そんな、意味を為さない雨が続いていた。
「いっそ、どしゃぶりになってくれればいいのにね」
「だな…」
唇を曲げて呟く少年に同意して、彼は身体を起こした。二十人は収容できる椅子とテーブルの組み合わせも、彼が腰を浮かせ立ち上がった今、使っている者は誰一人いない。開店休業も同然だった。
「智裕(ちひろ)さん、店閉めよっか?」
「そうしたほうがいいかもなあ。どうせこれじゃあ、誰も来ないだろうし」
窓の前に張り付いていた少年の提案にも同意する。もとより、選択肢はそれしかなかった。この仕事を始めて三ヶ月ほど経つが、それなりに賑わってきた店の主な客といえば女子高生で、昼休憩というピークを過ぎたばかりの時間に、客はほとんど期待できない。
それでも経営をやっていけるのは軌道に乗り切っていないという現状を考慮した、必要最低限の援助があるからだ。当然、贅沢をすることはできないが二人とも若さの割には物欲に乏しい。特に家計を握る小柄な少年のほうは、おそろしく倹約家だ。
以前、貯金のメリットと銀行への不満を熱く語っていた少年の姿を思い出しながら苦笑していると、不意に会話の合間、足音が聞こえた。からんころん、と真新しい扉の開く音を消すには充分のベルの音が続く。
「すみません、もう閉店しようと…」
「ワイン、置いてあるかしら?」
掛けようとした言葉の内容から大きく逸れた問いかけに、智裕はぽかんと口を開けたまま固まらずにはいられなかった。反射的に、料理を出す店なのだからあるのは当たり前だとか、そういえばロゼワインが切れていなかったっけだとか考えながらも、思考が停止して言葉が出てこない。
「アロフェンさん…?」
「涼芽(りめ)、あなたにも勿論関係のある話だけど…わたしが連れてきたお客様は、どうやら智裕の知り合いみたいよ」
「え?」
彼女が視線を向けながら言ってきた言葉に、無意識に智裕の表情が強張る。あまり、積極的に関わりたいと思う知り合いはいないからだ。血の繋がった人間…兄同然の人とさえ、この半年ほど接触を絶ってきた。そんな自分に、しかも彼女を通して再会しようとする人間なんて見当がつかない。
赤紫色の髪につく雫を払いながら、アロフェンは女神のごとき微笑を浮かべた。しなやかな身体つきだけでなく、性格からにじみ出る表情にも成熟した美しさが感じられる。恐れるものなど何一つないのだと、錯覚させるように。
誰一人として、この世界に生きる人間は強くなどない。だがこの力が怒りも憎しみも駆り立てるのだと、智裕は気付き始めていた。異能がなければ二人と関わらずに一生を終えたのかもしれない、そう想像する。もしも、失わなければ…。
「智裕…!」
我に返り相手の名前を呼び返すのには、一度口内に溜まった唾を飲み下すだけの時間を要した。一度飲んでも、飲み干せはしないけれど。
「ミオーレ、お前…」
「探したんだよ、わたし!新聞とかニュースであのことを知ってから、ずっと思ってたんだ」
懐かしい顔。空白の年月を引いても、身体こそ成長すれど彼女は変わっていなかった。そう思いながら、必死で言いながら近付いてくる彼女を見つめる。最後に彼女と会ってからおよそ四年だと、すぐに脳が知らせてきた。
「ずっと、心配してた。もしかしたら智裕が『レセレファクト』にいるんじゃないかって、ずっと捜してたの」
その眼差しは真剣で、少しだけ哀しげで、それでもあのミオーレなのだと、智裕には理解できた。彼女は彼女で、本当に変わらず自分のことを見ている。遠縁ではあるが、それでも数少ない見知った血縁者。
だが智裕は不意に不安を感じていた。自分は彼女のことを思い出せる。変わっていないと思う。けれど、彼女にとっての自分もあの頃と同じなのか、自信は持てなかった。逆に確信めいて思う。今の自分は、随分と酷い人間に見えるのではないかと。
それでも再会できた嬉しさに智裕はそっと笑みを浮かべて、「ごめん、ありがとう」と心の底から言いながら彼女の頭をあやすように撫でた。
それが約四年ぶりの再会の日で、彼女のことを何も分かってあげられなかったときだけれど。全てが分かった今、もしもこのときに戻れたとしても。きっと自分は彼女に何も言ってあげられなかっただろうと、智裕は後悔と自己嫌悪を抱きながら思った。
■サンプル2
乾いた風があたしの頬を撫でていく。土は固く不愉快な音を靴に刻ませて、あたしの心を乱す手伝いをした。言い訳とか誤魔化しとか、そんな未練がましいことをする気にはなれなかった。いや、させなかった、のかもしれない。
…こんなところ、あたしは知らない。それに漠然と思う。ここには日本でも、そもそも地球でもないのだと。
確信的にあたしの胸の鼓動が、そう告げていた。
世の中は綺麗なんかじゃない。あたしは世の中の大人を、誰一人として信じることが出来なかった。その醜さを、そして無能さを嫌というほどに知っていたから。人間は人間の悪意が邪魔するから、本当の意味での進化なんて出来やしないのだ。
知ってる?この世の中を会社に例えるなら、誰も来ないような場所に店舗を作って資金を無駄遣いするような決して褒められない会社。自分が美味しい思いをするならそれでいい。そんな人が少しでもいれば子供は何も信じられなくなる。そんなことなんて知らない、本当に努力している人を裏切り続ける社会が形成されてる。あたしはだから、自分の育った場所が大嫌いだった。
でもあたしだけは、絶対にそんな人間になんてなりたくない。そう思って生きてきた。それは今だって変わらない。今いるこの異世界はまさに、悪意を具現化した世界。騙したもん勝ち。負けた奴はそこで終わり。命は賭けの材料。あたしは、あたしたちはそんな騙し合いの世界に放り出されたんだ。
身元を分からないようにするためか、フードで顔を隠した女の子、REN-GE(れんげ)。馬鹿だけど周りの状況をよく見てる金持ちのお坊ちゃま、氷雨(ひさめ)。そしてあたし、サユコ…本名は違うけど、彼らにはこう名乗ってる。…ま、この二人だって明らかに、本名じゃないしね。
あたしたち三人はここからすると異世界…地球、それも同じ日本から来た人間として同盟を組んでいる。互いが騙されたら互いが助け合う。生活するのに必要なものは全て共有する。絶対に切っては切れない関係、裏切り以前にあたしたちは、それぞれの長所を重ね合わせなければここでは、生きていけないのだ。
あたしは「頭脳」。その時その場所の状況のなかで最善の策を選ぶ。
氷雨は「知識」。一番最初にこの世界へ来たために誰よりもある常識で、上手く立ち回る。
REN-GEは「体力」。女の子だから腕力はまだしも、桁外れの体力と格闘技で戦う。
いつしか、あたしたち三人のことをこの世界の人間はこう呼ぶようになっていた。
デザートイーターイーター。
他人の大切なものを奪う、そんなことを生き甲斐とする者から転じて、他人の菓子を無断で食す者。すなわちデザートイーター。そいつらの大切なものを更に奪うのがあたしたち、ってことか。心の醜い連中を嫌うあたしにとっては、奪うなんて不名誉とも言える称号だ。
…けどまあ、その響きは嫌いじゃないかもね。思ってあたしはまた、異世界での朝を迎えるんだ。いつかこの生活も終わる、そう確信を抱いて。
■サンプル3
世の中はなんて悪に満ちているのだろう。
そう思うひとりの男が心荒んだ世界にいた。正義を愛し、悪を憎み、そしてただひたすらに真っ直ぐなその男の名はアッシュ・グレイ。組織体質のとある市警でいても尚、汚れずに戦っている。だがある事件に巻き込まれたことをきっかけとして、アッシュはある男と出会うことになる。最初は反目していたものの、やがて共闘するたびに友情が芽生え、そしていつしか唯一無二の相棒へと…
………。
「って、アホかぁぁぁ!!」
ちゃぶ台が目の前にあったら絶対に引っくり返してる、そんな勢いで俺はツッコミを入れる。あげた絶叫で通り過ぎていく人たちの冷たい視線が向けられたが、そんなもんいちいち気にしてられるか。
「何勝手なナレーションつけてるんだよ、お前は!」
“いや、細かいことは気にすんなよ”
「細かいことじゃないだろうが!!大体何だ、ロス市警のアッシュ・グレイって」
“ロスだなんて言ってねえし”
「市警って言ったらロスに決まって…じゃない、嘘八百言うな」
言っておくが俺は、警察の人間でもなければアメリカ人でもない。先祖を何処まで辿ってもおそらく日本人で、当然ながら生まれも育ちも日本、それも関東で、ついでに言えばアメリカどころか外国なんざ行ったことがないくらいの貧乏育ちな人間だ。…いやごめん、俺も言っててちょっと虚しくなった。虚しさのあまり思わず、額に手を当ててうなる。
「ちなみに、唯一無二の相棒ってのはお前のことか?」
“へへ、分かってんじゃねえか”
この話の流れから考えればお前のことに決まってるだろうよ。
胸中で思いながら、俺は小さく溜め息を吐いた。まったく、いつものことながら訳の分からないノリだ。何を言い出すかは分からないが、言い出したことに関して俺がツッコまないことは一度もない。それは残念なことと嘆くべきか、確実だった。
「第一お前、それ何処の映画の話だよ」
“あ、やっぱベタ過ぎた?”
「ベタっつーかむしろ胡散臭いな」
“失礼な、これでもオレは作家志望だぜー”
「…そのオチのために言い出したんじゃないだろうな」
有り得る。っていうか絶対そうだ。もうツッコまないぞ、俺は。疲れるし。
“ちぇ、せっかく暇つぶしさせてやってんのに冷てえなあ”
「依頼人との待ち合わせのたびにこれじゃあ、俺の身がもたん。…お前、物のくせにお喋りなんだよ」
“あ、差別”
「うるさい」
手のひらサイズの携帯端末、その画面がまるで嘘発見器…じゃない、心電図のように振れている。それがこいつが生きている証だ。
何もこの時代、人語を解する物が存在することは珍しくない。いわゆる「物に命が宿る」とか、「人工知能」とか、そういう理屈じゃあないんだけどな。そのあたりの話はまた、別の機会に譲るとするよ。
“おい、お客様のお出ましだぜ”
「…そのへんのチンピラが出てきたような言い回しをするな」
言いながらも俺は、こちらに向かって迷わず小走りしてくる人物の人相と、手紙とともに送られてきた写真に写っていた少女を重ね合わせていた。なるほど、確かに面影ははっきりと残っている。
さて、ここからが本当の始まりだ。便利屋として生きることを決めてからの、最初の依頼なんだからな。 |
|



|