
 |
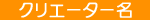 |
愁水 |
 |
愁水と申します。主に「エリュシオン」でMSとして活動しております。お客様のキャラクターの魅力を最大限に引き出せるよう、努力していく所存です。ご縁がありましたらよろしくお願い致します。 |
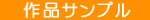 |
■サンプル1
「En-Trance」
祖母が言っていた。
世界は楽譜の上に成り立っている音符みたいなものなのよ。だから貴女は自分を誇ればいいの。貴女の歌はいつか、世界を響かせるものになるわ。
そう信じたまま、祖母は死んだ。
**
オト。
空気の様に軽やかで、水滴の様にたゆたう歌が響いていた。
人魚に愛されたかの様なその声のメロディが、ふっと途絶える。声の主はベッドに預けていた腰を浮かせて、
「兄さんと姉さん、無事だといいな……」
自室の窓を開け放つ。
鳥籠を彷彿とさせる窓柵にそっと触れた彼女――マヤは蒼穹のパレットを仰いだ。空はあんなに美しいのに、自らの胸の内はくすんでいる。暗に揺れる理由。
――私には何の力もない。
人や家畜を襲う存在、マモノ。正体不明の世に蔓延る畏怖。
一説には悪魔が産み落としたモノ、人間に罰を与える為に天使が翼から生み出したモノ、と。だが、確証たる説はない。
マヤは兄や姉の様に、剣や魔法の才覚があるわけでもなかった。日々、マモノ討伐の依頼の為、身を粉にする兄姉はマヤにとって尊敬と懸念の存在であった。
「(私が誰かの為に出来ること……私、私には……何もない)」
強いて一つ。祖母が誇れ、と言ってくれたこと。
「……歌うこと、なのかな」
マヤは細い声で呟くと、もう片方の手を何気なく窓柵に添えた。その瞬間、
軋む金属音。
手の平からソレが否応なく伝わってきた時には、既に遅かった。空を掴むも自らに翼などなく、外れた鳥籠を茫然と視界に入れながら、マヤの身体は屋敷の三階から落下した。
――はず、であった。
音楽が聞こえる。
天国で奏でられるオトがあるとしたら、こんな音色なのかもしれない。
「…………私、生きてる?」
意識を失っていたのか、そうでなかったのか。非常に曖昧な時の流れに身を委ねていた様な感覚。少なくとも、一切の衝撃を受けなかったのは確かだ。
髪と服の乱れを整えながら、マヤは伏せていた身体をゆっくりと起こす。
「ドコだろう……ココ」
不安に翳り、琥珀色の大きな瞳に映るのは見覚えのある庭ではない。其処は、何かが捩じれた寓話の挿絵――という印象。
澄んだ空気の中央には大樹、壁と天井には十字架や蔦、花々をモチーフにしたステンドグラス。其処から差し込む光は雪の結晶のように美しく、不安定で。床の所々には墓石の様なものが埋め込まれている。そして、絶妙な加減で響くヴァイオリンの波がそれら全てを“調和”しているかの様で――。
広くはないけれど、不思議と“納まる”空間。
「誰か、いるの……?」
小さく漏らしたつもりが思いの外、反響した。すると、不意に音楽が途絶え、
「――いるよ」
遅れて言葉が降ってくる。
頭上だ。マヤが大樹を見上げると、フワリ、太い幹から何かが落下してくる。後退りをする余裕もなく、半ば茫然と前にしたのは――、
「こんにちは。ふふ、可愛らしい客人だね。何日ぶり……いや、何ヶ月――ん? 何年ぶりだったかな? トコヨの秒針は旋律を奏でないから音譜を忘れてしまう」
一人の男。
年の頃はマヤよりも五つか六つ、上、恐らく二十代半ば辺りであろうか。白に近い銀色の髪。肩には外套を掛け、慎ましさな黒を基調とした装いだ。首に下げた紐組みのネックレスが、服の一部の様に釣り合っている。
そして、左手にはヴァイオリン、右手に弓。思考するまでもなく、この場を支配していた奏者であろう。
「俺はカデンツァ。此処、トコヨの独裁者だ。君の名を聞いてもいいかい?」
切れ長の吊り目――カデンツァと名乗った紫水晶の瞳が、マヤを映して微笑む。
何故だろう。マヤの全身からするりと、警戒の糸が解けていく。不思議と、得体の知れないこの男に恐怖が湧かないのだ。本能的な“何か”がそう告げている様な――……。
「……マヤ」
「マヤ、か。無垢で可憐な響きだね」
「……あ。ええと、その……ココって、」
――“トコヨ”。彼は先程、そう言っていた。馴染みのない言葉。馴染みのない空間。自分が知らないだけで、現実に存在する確かなモノなのだろうか。
いや、そもそも自分は本当に――、
「君は死んでないよ。大丈夫、俺も、この空間も、幻じゃない。此処は在るべき境にあり、在るべき人にしか訪れることを許さない域だ」
胸の内が、安堵の灯りを照らした様な気がした。その言葉が信じるに値するかどうか、何を持って基準なのかどうかもあやふやであるというのに、見透かされた心は涼やかな声に包まれる。
「じゃあ……夢、でもないの? だって、その、とても不思議なことが起こったの。私、自分の部屋に居たんだけど……窓柵が外れて、一緒に落ちてしまって……でも、その一瞬の後、場面が変わるみたいに、」
「気づいたら此処にいた?」
「――っ! そう! ねぇ、貴方はココの住人なんでしょ? 私に何が起こったの? 何故、私はココに来てしまったの? 私はちゃんと元の世界に帰ることが出来る? ねぇ、お願い。何か知っているなら教えて欲しいの!」
焦りの余り、うわずった早口からマヤの感情の揺れが伝わる。問いの渦にカデンツァは気分を害することもなく、穏やかな眼差しを彼女に向けたまま、
「君がトコヨに来たのは、君がそう望んだからだ」
教本を読むかの様に言った。そして一度、睫毛を伏せると、マヤの横を通り過ぎてある位置に落ち着く。
――ピアノだ。ステンドグラスの光を浴びて、オーロラの如く輝いている。カデンツァは手袋を口で外すと、言を次いだ。
「――マヤは、“力”を切望したね?」
突然、閃光が瞬くようにマヤの脳裏で彼の言葉が爆ぜた。
――どうして。そう、どうして。カデンツァの言葉が嘘ではないことを知っている。故に、何故、何もかも見透かされているのか。
力のない私。力を欲する私。心の深い部分で、どちらも既に理解している“私”。
彼は大樹の根元で枯れかけていた花――牡丹であろうか、それを一輪摘むと、ピアノの端に置く。
「俺が叶えてあげよう、君の全てを」
彼の行動の答えを聞く間も、知る間もなく、カデンツァは穏やかな表情そのまま、ピアノの前へ腰を下ろす。そして、白い鍵盤を軽やかに弾いていく。
「実際にやってもらった方が早い。さあ、歌ってごらん――マヤ。君の“特別”が“全て”へと進化する瞬間を見せてあげよう。それが、俺の役目だからね」
言うなれば、混乱と誘惑。
何故、自分の願いも、自分の誇りも、カデンツァの瞳に映っているのか。それらに五体を縛られながらも、マヤの眼差しも、声も、心も、彼の幻奏に縋っていた。
何が正しくて、何が間違っているのか。ただ、この渇望は真実で、自分には歌うことしかない。
ならば、
――歌う。柔らかな光に、大樹の猛き生命に、肌を愛しく撫でるメロディに乗せて。
すると。命を潰えようとしていた牡丹に変化が訪れる。その身を淡い輝きと色が灯り、それが包みきって弾けた瞬間。
「――……っ!? ……嘘……咲いた……まさか、命を吹き返した、の?」
「ああ、そうだよ。君の力だ」
最も美しい時の姿へ変えた牡丹の軸をカデンツァは摘まみ上げる。そして、初めて見せる真摯な目元で彼はマヤに言った。
だが、代償が必要だ――と。
「この力を得たまま元の世界に帰りたければ、代償を払ってもらう。君の場合は……そうだね。
――“聴覚”だ。
ふふ、怖がらないで。これは俺からのプレゼント」
マヤの怯えた瞳を、鮮やかな牡丹の色で抱擁するかの様に。カデンツァは、そっと彼女の左の耳元へ癒された命を添えた。
「この牡丹を耳元に挿していれば、音は消えない。平素と同じに聞こえる。だが、大切にしてくれ。枯れることはないが、壊れないわけではない。
――さあ、どうする? マヤ。
選択の時だ」
マヤは唇を結ぶ。
得ることが幸せとは限らない。知らないことが幸せなこともある。だが、自分は知ってしまった。力の内と外。そんな境界など、もはや自分の中では些細なものとなってしまったことに気づいた時、
彼女は笑った。
世界に響く“力”の為なら、“アクマ”の声にも耳を傾けるだろう。誰だって、きっと――。
■サンプル2
「生首は静かに笑う」
「ねぇねぇ、ちゃんと聞いてる〜? 那岐」
「あー、ハイハイ。頭カチ割れてるけどちょっと可愛かった女子がなんだって?」
「実はこの高校の教師と不倫してたんだって! あ、十年も前らしいけどね。卒業したら結婚しようって約束してたんだけど、教師の奥さんが妊娠しちゃって。突然別れ話を切り出された彼女は逆上。教師を刺して、ココの屋上から飛び降り自殺したらしいんだよね〜」
「………」
――重い。
昼飯の話題にしては重すぎる。
それにココって……その女子生徒の自殺現場で俺達、今飯食ってるってこと?
唐揚げを口に入れようとした俺の箸がぎこちなく止まったのを見て、梓が笑顔のままあっけらかんと言う。
「あ、大丈夫大丈夫〜! 彼女はもうキレイさっぱり成仏したよ。僕に祓い残しはなし!」
「……食器汚れみたいに言うなよ」
おにぎりを頬張る梓を横目に、俺は溜息をついた。まぁ、悔いや恨みのある幽霊が成仏できたのならそれに越したことはないか。すんなりそう思えるようになってしまったのは、紛れもなく梓のせいだろう。
子供の頃から幽霊やら妖怪やらが見えていた梓にとって、彼らが見える世界が日常だった。
やれ、あそこに血を流した女の人がいる、頭が皿のヒトがキュウリをかじっている、など、目にしたコトをしょっちゅう口にしていたらしいが、まぁ、見えない人の方が殆どなワケで。同年代のガキからは気味悪がられ、大人からは奇怪な視線を受けていたらしい。成長した今でこそ、自重して世間と普通に接することができているが……。
この天然はにわ顔にも笑えない過去があったんだよなぁ……。ふと、思い出し、梓を見る。
「ん? ばに? はぼにばびがふいへう?」
「ちょっ、おい! 米粒米粒! 米粒飛んでるっつーの!」
……思えばあの日。
中学の入学式で初めて会ったこいつは、体育館の裏で泣いていた。最初はいじめにでもあったのかと思いきや、実は幽霊のお祓いに初めて成功して泣いていたのだ。苦しんでいた幽霊をやっと送り出せたと言って、ぴーちくぱーちく泣いていた。
第一印象は勿論、変な奴。
しかし、そんな状態の梓を放っておく事もできず、俺は成り行き上、梓が落ち着くまで側にいることにしたのだが……今思えば、それがいけなかった。
梓はぽつぽつと身の上話をしていたらしいのだが、正直この時は面倒で、俺は適当に相槌をうっていただけだった。
つまり、全く聞いていなかったのだ。
梓にしてみれば、自分の話を疑う事も気味悪がる事もなく聞いてくれる人間に初めて出会ったのだろう。すっかり懐かれてしまうことに。
……言えない。今更、幽霊の話なんて本当は全然聞いていなかった、実は幽霊など信じてもいないなんて、口が裂けても言えない。喋ったもんなら俺、絶対梓に呪われる。
――と、出会った当初はビクついていたが、毎日毎日幽霊話なんて聞かされると、実は本当にいるんじゃないかと思ってしまうもんで。ある意味、洗脳? 偶に自分がコワくなる。
「ねぇ、那岐ぃ。今日那岐のウチに遊びに行ってもいい? 昨日発売したホラーゲーム一緒にやろうよ。ていうか、やってね」
「は?」
俺のビミョーな心配をよそに、呑気に梓が今日の予定を聞いてくる。というか決定される。
不思議なことに、梓はホラーゲームが大の苦手なのだ。だが、興味津々。なにこのコワイもの見たさの女子みたいなヤツ。キモイ。自分でやるのは怖いものだからいつも人にプレイさせ、本人は俺の腕にひっつきながら画面に食いついている。
マジ、邪魔。
しかし……この手のゲームを持ってくる度思うのだが、何故!? 幽霊など日常茶飯事の梓が何でホラーゲームを怖がるのか、未だに理解できない。勿論、理由を聞いたことはあるが「真夜中トイレに起きた時に、トイレの目の前でどっかの誰かが丑の刻参りやってる方がよっぽど怖くない」というワケのわからない返答。
……俺だったら確実にノックアウトだよ、その状況。
「……ま、別にいいけど。――ん、今日!?」
だっ、駄目だ!! 〝本堂でお祓いがある〟って朝、親父が言ってたんだ!!
「ゲームは今日無理だ」
「え、何で?」
「ウチ以外だったらドコでもいいけど」
「は? だから何で? 家で何かあるの?」
「いや、別に……」
「だったらいいじゃん。僕、このゲーム楽しみにしてたんだけど」
「…き、今日はゲーム厄日、だから……」
「………。何か隠してるでしょ、那岐」
勘ぐる梓の視線が痛い。どーにかして誤魔化さないと! 誤魔化さないと! 誤魔化せ、俺!!
結論。
「駅前の甘味屋の金魚鉢パフェ食べに行かねぇか? 奢るぞ」
「フォォォォウ!! 金魚ーーー!!」
作戦成功。梓が甘味大魔王で助かった……。
町外れにある神社、そこが俺の家。
由緒正しいといえば言葉はいいが、実際はかなりガタがきているボロ寺。その寺の神主である俺の親父は、梓のように生まれつき霊能力がある。どうやら代々受け継がれているらしい。驚くことに、かつては俺にもあったという。
四、五歳の頃、交通事故にあった俺は、頭を強打して意識不明の重体を負った。奇跡的に意識は取り戻したのだが、事故後の俺は、まるで後遺症のように霊能力のスイッチがオフになっていた――らしい。
……自分のことなのに、記憶にないだけでまるで人ごとのように感じてしまう。ゾッとしない話だ。
退院後、両親は霊関係専門の医者に俺を見せに行った。だが、どこを尋ねても俺の霊力が消えた原因は分からなかった。
元々霊関係の医者は少ない。藁をも縋る思いで最後の医者に見せに行くと「わからん」の一言。「おやおやぁ」「あらあらぁ」、そんなノリの俺の両親が、この時ばかりは二人揃って医者にプロレス技を仕掛けたというのだから……まぁ、よっぽど頭にきたんだろう。
代々受け継がれてきた能力が俺の代で途絶えてしまうかもしれない。
初めはそんな心配を両親はしていたらしいが、流石は天然のほほん夫婦。今では「気楽にしてればいいよ〜、霊能力がなくたって那岐は那岐なんだからさ〜。いつかパッと戻ってくるかもしれないし」と俺より気楽な両親。
……正直な話、霊能力なんて戻ってきてほしくない。
映画やゲームの恐怖は作り物だからまだいい。だが、心で在るかどうかの否定をできないものは、とても恐ろしい。確かに〝そこ〟に存在していると、霊能力が戻ったら嫌でも認識してしまうはず。
霊が成仏できてよかったな、なんて思えるのは所詮、俺には関係ないから。
霊が徘徊している世界なんて、考えただけでも気味が悪い。
「出汁巻き玉子もーらい!」
「――あ」
止める間もなく、弁当箱から最後のおかずがかっ去られた。何も知らない梓が幸せそうに食べる姿を見て、少々罪悪感……。
「那岐、どうしたの? さっきから変だよ? 顔は元から変だけどさ」
「あ? ……いや、何でもな――ん? 今なんつった?」
「もうすぐお昼時間終わるね〜。お腹いっぱいだ〜ご馳走さま」
「……」
もし、俺の事情を知った場合、梓は俺にどう接するのだろう。
仲間に引き入れる為、力を取り戻させようと躍起になるのか。それとも、今まで通り友達として接しようとするだけなのか。
「あ〜、金魚鉢パフェ楽しみだなぁ〜! 那岐にも少し分けてあげるね! あそこの白玉とあんこって絶品なんだよ〜」
……純度百パーセントのこの笑顔。青い空と日の光をバックに、憎らしいほど爽やかだ。
何だか、どうでもよくなってくる。
「む。何笑ってるのさ、那岐。白玉とあんこバカにしないでよ」
……。
本当に、考えるだけムダだったような気がする。多分、多分だけどこいつは――。
「何その呆れたような顔ー! そんな顔するんだったらわらび餅もあげないからねー!」
「あーハイハイ。食うよ、いただきますよ」
こうやって普通に会話しながら弁当食ったり、遊んだり――そんな当たり前のことを俺と一緒に楽しめればそれでいいんだろうなぁ、と、恥ずかしながらもそう思ってしまった。
空を仰ぎながら、俺はふと、考える。
いつか、もしもいつの日か、梓と〝同じ世界〟を見ることになったら、俺は――……。
――ん?
―――あれ?
ぷかぷかと。〝ナニ〟かが俺の視界で浮いているのだ。
青い空に、常識的に考えて、それはもう不自然と。
「わ。すごいすだれ髪。え? 落ち武者? 身体どーしたのカラダ。え? さらし首にされたの?」
梓が〝ソレ〟と会話している。
俺の聞き間違いでなければ、落ち武者の首と。今、目の前に浮かぶソレも、そう見えるんですけど。
「ちょっと、那岐のことガン飛ばしても無理だよ。彼、幽霊見えないんだから――って、ちょっと聞いてんの!? このすだれ!!」
梓が何か叫んでいるが、俺の耳には入ってこない。
もうそれどころじゃない。落ち武者の首が――。
俺を見て、ニヤリと笑ったのだ。
|
|



|