
 |
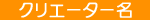 |
朝臣あむ |
 |
はじめまして、朝臣あむと言います。
どうぞ宜しくお願いします。
主に三人称でライトノベルなノリで作成します。 |
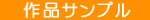 |
■サンプル1
華
花があった。
どういう名前なのかとか、どんな花なのかとか、そういった細かいことは覚えていない。
それでも、とても良い香りだったことだけは覚えている。
夏の日差しが少しだけ和らいで、着ている服の袖もほんの少し長くなった日だった。
そうこの日、僕は忘れられない体験をしたんだ。
***
残暑の中、セミが忙しなく鳴く。
その音を聞きながら借りた本を鞄に詰め、僕は図書館に向かっていた。
「早く冷房の効いた場所に行きたい」
無意識に呟いた僕の足は駆けていた。
この日は夏が戻って来たんじゃないかって、そう思うほど暑くて、自然と足取りも早くなっていたんだ。
そのせいかな。
余計に暑くて、きっと余分に汗を掻いていたと思う。
図書館への道のりは歩いて30分。走ると15分から20分程度で着く感じかな。
僕はそこへ向かうための大通りではなく、途中の分かれ道を右折する道を選んだ。
だってそのほうが数分だけど早く着けるから。
それに路地に入ったほうが、家の影で少しだけ涼しい。
僕は路地に入ると慣れた足取りで民家の間の小道に入った。
実はこの道も隠れたオアシスだったりする。
理由は比較的簡単なのだけど、まず地面がアスファルトではなく土だということ、そして民家に植えられた木が高くて、日陰がほとんどだということ。
これらを踏まえて、やっぱりここは隠れたオアシスだと思う。
「はあ、やっぱここは涼しい……ん?」
ふと足が止まった。
これから進む先に、何かある。
「なんだろう、あの黒いのは……」
不思議と怖さはなかった。
まあ、怖さがないのは真昼間だからと言うのもあるのかもしれなけど、今考えればあんなものが道端に転がってること自体がおかしいからだろう。
僕は道を塞ぐ黒い物体を覗き込むように近付いた。
そして――
「――ッ!」
声の無い悲鳴とはまさにこんな感じだろう。
僕の体からは一気に血の気が引いて、まともな思考さえも存在していなかったと思う。それでも僕は、いつの間にか覗き込んだ物体を観察していた。
黒い物体の正体は随分前に姿を消した黒いゴミ袋。そしてその口は結ばれるわけでもなく広がっている。
つまり袋の中身は丸見えで、その中にあるものに僕の思考が途絶えたわけだけど。
「……これって……死体?」
擦れた声でようやく言ったのがこれ。
僕は結局小心者だったわけだけど、いきなり目の前にゴミ袋に包まれた遺体が転がっていたら、普通の人はそうなると思う。
そして僕は、袋の中身を理解した瞬間、この場から駆け出していた。
必死に走って路地を抜け、大通りに出る。額にはびっしりと汗をかいて、息は完全に切れていた。
ぜえぜえと息をしながら暑い日差しを浴びていると、少しだけ思考が戻ってくるのを感じる。
「……あれって……本物、かな……」
切れる息の中でさっき見たものを思い出す。
パニックにはなっていたが、遺体は女性のものだったはずだ。
今思えば結構綺麗な人だったのではないかと思う。袋の中にある顔には血の気がなくて、長い髪が無造作に袋の中に広がっていた。
何か外傷があったかどうかは、今の僕には思い出せないし、たぶんそこまで確認はできなかったはずだ。
「……でも、なんで……」
ようやく息が整いだし、今度は額の汗が気になったときだった。
目の前にハンカチが差し出された。
それも綺麗な白いレースのハンカチで、少しだけ良い香が鼻をつく。
僕はハンカチからそれを持つ手に視線を移し、ゆっくりとその顔を上げ、
「――ッ!」
この日、2度目の声なき悲鳴が上がった。
ガクガクと震えだし、顔は完全に驚きと恐怖で歪んでいたはずだ。
「な、なななななな、なんでっ!」
悲鳴と叫びが混ざったような声を上げる僕に、ハンカチを差し出した白いワンピースを着た女性が、可愛らしく首を傾げた。
「あの……大丈夫、ですか?」
柔らかい声が気遣いを帯びて響いてくる。
その声に唾を飲み込むと、コクコクとだけ頷きを返した。
そんな僕の目は、驚愕に歪んだまま目の前の女性を見ている。
何故って……それは、目の前の女性がさっき見た遺体とまったく同じ顔をしていたから。
「あ、あ……貴女こそ……大丈夫、です、か?」
口元で引き攣った笑いを浮かべる僕に、女性はもう一度首を傾げた。
「わたしは何も。それよりすごい汗ですけど、何かご病気でもお持ちですか?」
女性の顔が心配そうに歪む。その顔を見ていて、徐々にだが僕の思考が戻ってきた。というよりは、落ち着きが戻ってきたのだと思う。
僕は女性の手からハンカチを受け取ると、必死で自分の汗を拭った。
「だ、大丈夫です。その……少し、見慣れないものを……」
「見慣れないもの?」
女性の声のトーンが少し下がった気がする。
けれどこの時の僕はそれに気付きはしなかった。ただ女性に見せた恥ずかしい姿を消したくて、そのフォローをどうするべきなのか、そればかり考えていた気がする。
「あはははは、暑くてきっと変なものを見てしまっただけですよ。だって有り得ませんもんね。道端に死体が転がってるなんて」
「ふふ。なんですか、それ」
豪快に笑う僕に、女性は口だけで笑って見せる。
目は笑っていない、どこか冷たささえも覗く笑みだ。その表情に、さっき見た遺体が鮮明に蘇った。
ゾクリと悪寒が駆けあがり、足が一歩、後ろに下がる。
「あはは……は、白昼夢ってやつですかね。あ、あの、僕、図書館に行くんで……失礼します!」
何故だかこの女性の傍にいたくない。
そんな気がしてハンカチを返すのも忘れて、駆け出していた。
そうして走って図書館に辿り着く頃には、また汗が吹き出していた。
だから女性に借りたハンカチで汗を拭おうとしたんだけど……
「ヒッ!」
パサリとハンカチが落ちた。
借りたときは白くて綺麗なハンカチだったそれが、いつの間にか真っ赤に染まり、手も真っ赤に染まっている。
「な、なんだよ、これ……」
ぬるりとした赤の液体から、ほんのり甘い香りと、鉄が錆びたような匂いがしてくる。
「これって……血?」
僕がそう判断したときだ。手を見つめる僕の目に白いものが入った。
ゆっくり視線を上げると、先ほどの女性が汗一つ掻かない状態で僕のことを見ていたんだ。
「!」
「わたしのハンカチ……返して……」
さっきと同じ、口だけ笑んで、女性は手を差し出してくる。
「ヒッ!」
僕はまた駆け出していた。
だって、女性の手は僕の手と同じように赤く染まっていて、白い綺麗なワンピースもハンカチと同じように赤く染まっていたから。
「な、なんなんだ、なんなんだよ、あれ!」
走りながら考えようとするけど巧く纏まらない。
とにかく逃げることしか頭になくて、僕は必死に走った。
必死に走ってどこをどう来たのかわらない。わからないけど僕は、ある場所に来ていた。
「……なん、で……」
呆然と佇む僕の前に、黒い物体が転がっている。
どこをどう逃げたらここに来るのかわからない。わからないが、確かに僕の目の前にはさっき見た遺体の入った袋が置かれていた。
広がった袋の入り口からは先ほどの女性と同じ顔の女の人が入っている。良く見れば白いワンピースを着ていて、それが赤く染まっているのが見えた。
「同じ人だ……――え?」
僕は我が目を疑った。
女性の懐に抱かれるようにもう一つ頭がある。よく考えれば袋はかなり大きく、膨らみも女性が一人にしてはあまりにも大きかった。
僕はそっと袋の中を覗き込むと、思い切り目を見開いた。
「あ〜あ、見ちゃった」
クスッと女性の笑い声がして振り返る。
赤く染まった女性が口だけではなく、顔全体に笑みを浮かべて僕を見てる。そして僕の体もその瞬間、赤に染まった。
そうして聞こえてきた、たくさんの声。
振り返ると沢山のパトカー、野次馬が蟻の如く黒い袋に群がっている。そして警察官の一人が袋を開くと、中から血だらけの女性と、僕が、姿を現した。
立ち竦む僕と、同じように立っている女性を、たくさんの人がすり抜けていく。
「僕も、死んでいた……?」
呆然と呟く僕の隣に、女性がやってきた。そして無言で野次馬の中の一人を指差す。
見覚えのある男だった。
その男を見た瞬間に、僕の中に記憶が流れ込んでくる。大通りを抜ける途中で横断歩道を渡ろうとした。
信号は青で、僕と一緒に大きな花束を持つ綺麗な女性が横断歩道を渡っていたんだ。
そこに赤信号で突っ込んでくる車がいて、僕と女性は逃げる間もなく弾かれた。
車は僕たちを助けるフリをして拾って、そしてあの男は路地にゴミのように捨てたんだ。
「あの男だ」
僕が呟くと、女性はゆっくり頷いた。
――翌日、恐怖に歪みきった顔をした男が、大破した車の中で発見された。
そして僕は、あの日からずっと横断歩道の前にいる。
その傍には綺麗な花が飾られていて、その隣に花を愛しそうに見つめる女性がいた。
僕と彼女はもう少しここで、あの日と同じことが起きないように見張っているつもりだ。
だって、もし同じことが起きるようだったら、犯人を懲らしめなければいけないから……。
……END
|
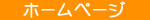 | 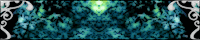 |
|



|