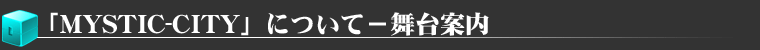
『破呼』:霜月玲守
毎日は、下らない繰り返しでできている。
俺は吐き気のするような坂を上りながら、小さくため息をついた。通っている高校に辿り着くためには、どうしても必要な坂道だ。しかし、自転車で通っている以上、坂道は限られた朝の通学時間にとっては弊害でしかない。なにしろ、坂が長すぎて途中から押して歩かざるをえなくなるのだ。
その分帰り道は一気に下る事が可能だが、帰りは大概友人と一緒だ。馬鹿な話を繰り広げながらだらだらと自転車を押しながら歩くことが多いため、心地よい風を受けながら下る事は少ない。
もちろん、だからといって自転車通学をやめるわけにはいかない。たかだか坂があるくらいで、それまでの道のりを徒歩にするなどということはありえない。
つまりは、今こうして遅刻寸前の時間帯だというのに、坂道を自転車で押して歩かなければならないというのが現実なのである。
「馬鹿らしい」
俺は小さく呟く。
たかだか坂道ごときで、こんな風に考えている自分が酷く矮小な生き物のように思えた。こうして高校に通っているのは、世間一般で中学校の義務教育を終えた後には高校に行くという事が普通になっているからだ。
中卒で働いている、立派な人もいる。そのまま高校に通わず、大検を目指す人もいる。
だけど、俺は惰性で「友達も行くし、普通行くから」とか言って高校進学を決めたのだ。決めた高校も、特にやりたい事があって決めた訳ではない。自分の成績内で、行けそうな高校を選んだのだ。あと考慮したといえば、通学時間だけだ。
もっとも、こういう坂の脅威は考えなかったが。
(なんで、こんな事考えてるかな)
俺は苦笑する。
どれもこれも、最近始まった進路指導の所為だ。担任と対面して「大学にいくのか」だとか「やりたい事はあるのか」だとか、全く俺が考えていない事を考えさせるようにしてくるのだ。その度に、俺は将来というものに不安を覚えていた。
やりたい事は、特にない。
自分の成績に見合った、多少は興味のある大学へと進むのだろう。例えば、工業大学だとか。そういう所に行くのだろう。
将来なりたいものとかやりたい事とかは、とっくの昔に見切りをつけてしまっていた。俺の成績では、どう足掻いたとしても昔なりたかった「医者」にはなれないのだ。
夢は夢のまま、どこかに消えてしまった。
とりとめもない毎日、変わらない毎日。全ては平凡という枠内に収まってしまった、自分の所為だ。
(もしも俺に、何か力があったとしたら)
俺は、ふと考える。
(もし絶対的な力があったとしたら、何かが変わっていただろうか?)
例え話だ。今最大限に見ることのできる、ありえない夢。
「……なんだ?」
ころん、と何かが足元に転がってきた。俺は押していた自転車を止め、下を見る。
「箱?」
それは、正六面体の箱だった。5センチ四方程度の、正方形によって構成された箱だ。
(落し物か?)
俺は何気なく、その箱を取ろうと手を伸ばした。落し物なら、交番にでも届けてやっても構わない。このまま行けばほぼ確実に遅刻する時間が、差し迫っているのだ。走って坂を駆け上る気なんてどこにもないし、それくらいならばこの小さな落し物を届ける為に交番に行くのも悪くないかもしれない。
ぱんっ。
箱を手にした瞬間、何かが弾けたような気がした。否、確かに弾けたのだ。俺の目に見えないだけで、箱が弾けたのは間違いがないのだ。
何故ならば、箱から何かが溢れ出して俺を満たし始めたからだ。
言いようもないものが、体中に流れていくのが分かった。輸血だとか、点滴だとかいうものに近いかもしれない。自分の中に何かが流れ込んでいく。
「……は、はは」
がしゃん、とちゃんと止めていなかった自転車が倒れた。片手で支えていた俺が、手を離したから。
「は、ははは」
からからと車輪が回っている。虚しく、それでいて規則的な音だ。
「はははははは!」
俺は箱を握り締め、笑った。
俺の中を満たす何かとは、力だったからだ。先ほどまで夢物語としてしか登場しなかった、絶対的な力。それが、箱から溢れ出して俺を満たしているのだ。
どうしてそのようなことが分かるかなんて、聞かれても困る。絶対的な力だという確信が、俺の中にはあったのだ。
予感ではない、確信。
俺はこの箱から溢れる絶対的な力を手に入れたのだと、確信した。だからこそ、笑いが止まらなかったのだ。
下らない毎日を過ごしていた馬鹿らしい自分は、既にどこにもいない。
今、ここにいるのは、絶対的な力を手にした存在なのだ……!
俺は笑いながら、頭の中を動かす。手に入れた力で何をしようかと、様々な考えを巡らせる。手始めに、こんな坂道は潰してしまえば良い。いや、高校も壊してしまおう。つまらないもの全てを破壊し、楽しい事だけを残す。
世界征服なんて、最高かもしれない!
「はは……は……」
俺は、がくん、と膝を折った。突如、体中の力がなくなったのだ。立っていられない程。
(なんだ?)
疑問は、すぐに解消された。箱の中から溢れてくる力が、俺を満たしきったというのにまだ溢れてきていたのだ。
力は一定量を越え、俺の体を侵食していく。
(なん、だ?)
手に入れたと思った力は、厳密に言えば手に入れたというよりも、ただ注がれたという方が近かったのだ。だから、許容量を越えてもまだ俺に注がれ続けられているのだ。
力が。
絶対的な力が。
俺を満たすのではなく、許容量以上に注がれている。
俺はぞくりと背筋を震わせる。自らの中に溢れていた優越感は消えうせ、止まらなかった笑いは凍り付いてしまっていた。これ以上力を自分に注がれたら、どうなるかなんて簡単に予想がつく。
世界征服も夢じゃなかった力が、俺を浸食し続けているのだ。
風船に、空気が送り込まれ続けているのと同じだ。俺は風船、力が空気。許容量を越えた風船が、どうなるかなんて俺はとっくの昔にしっている。
(怖い)
箱を手にし、初めて生まれた感情だった。先程まで確かにあった、実現した夢物語はホラーに変わってしまった。
(……恐い!)
箱を手放そうとしても、何故か俺の手は箱を放そうとはしなかった。手放すのが惜しいわけじゃないというのに、どうしても手から離れない。
(嫌だ……嫌だ!)
容赦なく注がれ続ける力に、俺は訴える。
(嫌だ嫌だ嫌だ!俺は、嫌だ!)
注がれ続ける力に対し、最早恐怖しか生まれなかった。あんなに下らないと思っていた毎日が愛しく、馬鹿らしいと思っていた自分が懐かしい。
「いやだぁ……!」
ぱあんっ!
空気を許容量以上に送り込まれた風船の末路は、決まっている。
割れて、弾けて、壊れてしまうのだ。
ようやく手から離れた箱が、ころころとどこかに転がっていく。それをぼんやりと見た俺は、薄れ行く意識の中で恐怖が安堵に一瞬だけ変わったのを確かに感じたのだった。
ただ、一瞬だけ。
葛城・文芽(かつらぎ あやめ)は、買出しの途中に倒れている高校生の少年を見つけて駆け寄った。
「おい、大丈夫か?」
文芽は少年を見、はっとする。
目はうつろで、口元からはだらしなく涎が垂れている。彼のものであろうと思われる、傍に倒れていた自転車の車輪がカラカラと音を立てているあたり、つい先程何かが起こったのだろうと容易に想像がついた。
文芽は掌を少年の目の前でひらひらと振って、彼の意識が既にない事を確認する。
自我の崩壊。
それが今の彼に、一番妥当な状態であった。
「まさか」
文芽は小さくそう言って、素早く辺りをきょろきょろと見回す。だが、何も視界には入ってこない。
「……エーテルボックス」
ぽつり、と険しい顔で文芽は呟き、ため息を一つついてから携帯電話を取り出した。
目の前の少年を乗せるための、救急車を呼ぶ為に。
<サイレンが遠くから響きつつ・続>