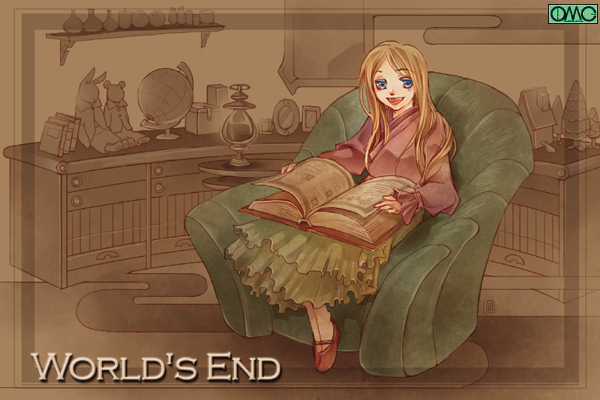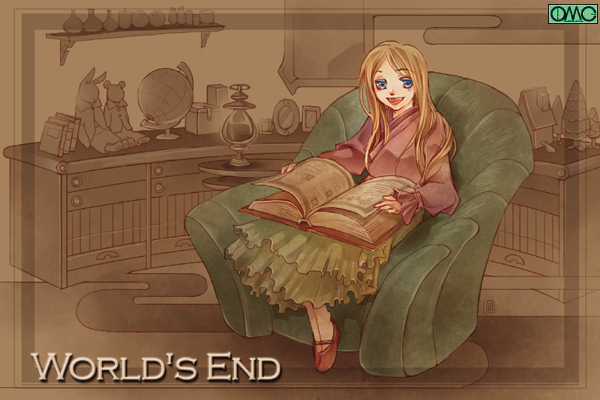■ワンダフル・ライフ〜特別じゃない一日■
瀬戸太一 |
|
【5199】【竜宮・真砂】【魔女】 |
お日様は機嫌が良いし、風向きは上々。
こんな日は、何か良いことが起きそうな気がするの。
ねえ、あなたもそう思わない?
|
ワンダフル・ライフ〜ミス・レイン
それは、しとしとと小雨がぱらつく日のことだった。
私はいつも通りカウンターの席に腰掛け、机の上に置いた机を覗き込みながら
自分の金色の髪をブラシで梳かしていた。
私の細く長い髪は、雨が振ると殊更ぼわっと広がってしまう。
…これがなかったなら、雨の振る日は喜ばしく感じるのに。
ハァ、と溜息をついてブラシを机の上に置いた。
いくら梳かしても、やはりぱさぱさするのだ。
リースなんかがこの私の様子を見たら、魔法でワックスを作ればいいのに、と哂うだろう。
でも生憎、何でもかんでも魔法で解決するのは良いことだとは私は思わない。
…ほんの少し、私がリース程器用に魔法薬を調合出来ない羨ましさも入っているのかもしれないが。
―――ハァ。
もう一度溜息をつき、私は鏡を覗き込んだ。
どうにかならないものかしら、この猫っ毛は。
そんな平和なことで悩んでいるときに、彼女がやってきたのだ。
「いらっしゃいませ。何かお探しでしょうか?」
私は手を胸の前であわせて、腰ほどの高さの台に並べている品物を眺めている人物のほうに近づいた。
普段から大して客の入りは多くないこの店は、雨の日になると一層客足は遠のく。
そんな雨の日にやってきた客らしき人物に、私は心が躍った。
心なしか声もはずむ。
「何かご希望があれば、承りますよ。世界に一つだけの品物を作ることも可能です。
どうぞお気軽に―――」
―――仰って下さいな。
そういいかけた私の口は、言葉を閉ざした。
街を歩いていれば振り返ってしまうだろう美貌、歳を経ているからこそ感じられる浮き立つような”女”の匂い。
綺麗に着こなしている和服のうなじは、同性の私でさえも目を見張るような白さだった。
見覚えがないはずなのに、どこかで感じた覚えのある眼差し。
そんな瞳が私に向けられ、思わず私は固まった。
菖蒲が艶やかに舞う和装と漆黒の艶やかな髪、そしてしとしとと穏やかに振る雨の音。
その全てがまるであつらえたようにマッチしていて、良く知った自分の店の中なのに、まるで別世界のような。
そんな一種異様な雰囲気は、当の彼女によって破られた。
「…あなたがルーリィさん?」
「へっ?は、はい?」
…いや、この水墨画のような世界を壊したのは、きっと私自身だ。
なんでこんな、阿呆のような返答をしてしまうんだろう。思わず頬が赤くなる。
そんな私を見て、和装の女性はコロコロと軽い声をあげて笑った。
「話に聞いていた通りのお嬢さんね。初めまして、私は竜宮・真砂(たつみや・まさご)と言います。
先日は孫がお世話になりました」
そう言って軽く頭を下げ、にこりと微笑む。
私はというと、目を丸くしてきょとんとした表情を浮かべながら、和装の女性―…真砂を見つめていた。
話に聞いていた―…というからには、以前この店に訪れた誰かの知り合いなのだろうか。
そういえば、何処となく眼差しが誰かと似ている。誰とは思い出せないが。
ということはその誰かの身内なのだろうか―…孫といっていたし。
――――孫?
「ま…マゴ、ですか?」
「ええ、そう。不肖の孫、そして弟子。あなたに大変お世話になったようで、私も拝見させて頂いたわ。
私からもお礼を言わせて頂戴。恥ずかしながら、私にはああいうものは―――」
「あ、あの!マゴ…って、あのマゴですか?マゴといっても…ああ、もしかして馬子ですか?
おかしいなあ…ごめんなさい、ちょっと記憶があやふやで。うちにお馬さんなんて来たかしら?」
「………ちょっと待って頂戴、落ち着いて。誰も馬の話なんてしてないわ。
それに馬子っていうのは馬のことじゃなくて、昔、人を乗せた馬を引いていた人のことを言うのよ」
「はぁ、そうなんですか。勉強になりました!…それで、真砂さんでしたっけ。貴女は一体?」
「………………。」
そのまま暫し、二人で見詰め合う。
明らかに会話が食い違っている。だがお互い、その食い違った理由が分からなくて、呆然としていた。
そして暫く見詰め合ったあと、ふぅと息を吐いて真砂が言った。
「…とりあえず、これをどうぞ」
真砂の腕から、私へとさらりとした肌触りの良い風呂敷に包まれた、長方形の箱が手渡された。
そしてどこか困ったような笑みを浮かべて言った。
―――落ち着いて、お話しましょうか。ゆっくりとね。
■□■
「………え、真砂さんってお孫さんがいらっしゃるんですか!?」
「…初めからそう言っていたような気もするけど」
私は目を丸くして、苦笑いを浮かべている真砂を眺めた。
彼女の外見は20代半ばほど。とてもじゃないけれど、孫がいるようには見えない。
「あなたなら、わざわざ説明しなくても分かってもらえると思ったんだけれど。同類のあなたなら、ね」
そう言って真砂は、悪戯っぽく笑った。
私は苦笑を浮かべ、頭をかいた。
「あはは…ごめんなさい、あんまりそういう勘が鋭くないものだから。
へえ…でもすごいですね。本当のお歳とかは―…聞かないほうがいいですね」
「そうね。秘密があるほうが魅力的だと思わない?」
「…真砂さんは何もなくても、十分魅力的ですよ」
あまりに和服と、黒髪と、雨が似合っていたものだから、初めて目を合ったときに硬直してしまった、
なんていうことは恥ずかしいので言わないことにした。
…それにしても。
「あの人魚さんのお師匠さんだなんて思いませんでした」
私は敢えて、お婆さんとは言わなかった。この妙齢の女性にその形容詞は似合わないと思ったからだ。
真砂はそれを聞いてころころと笑い、
「そうかしら。私、あの道具を作るほどの魔女さんなんだから、きっと人目で見抜くと思ったんだけれど。
…少し若作りしすぎたかしら?」
「いっ、いえいえ、そんなことないですよ!私、思わず見惚れてしまったもの」
「あら。それは光栄だわ」
ふふ、とにっこり微笑まれ、思わず口に出してしまった言葉に私は頬を赤くした。
…どうも、この匂いたつような色気を持つ女性というものは、私は少し苦手なのだ。
苦手というか、…そう、憧れの先輩を目にしているようで、常にドキドキする。
それに何より、ある意味でこの真砂は私の先輩でもある。
分野は違うが、もう何世代も前の”魔女の”先輩。
…私が緊張するのも当たり前だ。
私の婆さまも違う意味で緊張するが、彼女に対する感情とはまた別。
それに、先日店で会ったあの人魚の少女の祖母だともいう。
…私の祖母が真砂のような女性だったら、私は一体どうなっていたのだろう。
まるで姉のような祖母。…感覚が狂いそうだ。
「…ルーリィさん?」
黙りこんでしまった私を、不思議そうな顔で真砂が覗き込んでいた。
私は慌てて首を振り、
「え、いえ、何でもないんです。気にしないでください」
「そう。なら良いんだけど…そうそう、これ、良かったら食べて頂戴な」
そう言って、真砂はテーブルの上に置かれている重箱を薦める。
重箱の中には、ぎっしりとお茶請けのお饅頭や綺麗に象られた和菓子が詰められていた。
それも3箱。とてもじゃないけれど、今この場では食べ終わらないだろう。
この全ては、真砂が「孫がお世話になったので」と持ってきてくれたものだ。
私は一つ桜の形に作られた和菓子を手に取り、口に運んだ。
しつこくない餡の味が口に広がる。
「…美味しいですね、これ」
「そう?良かった。きっと余るだろうから、ルーリィさんの使い魔たちにもどうぞ」
にっこりと笑う。
今この場にあの子達はいないけれど、真砂には読まれている。この家の二階に、私の使い魔たちがいることを。
「…はい、遠慮なくそうさせてもらいます」
私は頷いて言いながら、真砂の様子をじっと観察していた。
優美で穏やかな物腰、だけども全てを見透かすような瞳を持っている。
…そうだ、本来魔女というものはこうあるべきなのだ。
「………いいなあ…」
「え?」
私がぽつりと溢した言葉を、真砂は聞き逃しはしなかった。
「何が?」
そう、にっこりと微笑んで尋ねてくる。
私は聞き取られたことに戸惑い、どもりながら言った。
「あ、その…あ、雨が似合うっていいですねって!」
「…雨?」
かぁぁぁぁ。
私は何を言ってるんだろう。思わずまた頬が赤くなる。
「へ、変かもしれないけれど。真砂さんって、雨が似合うなあって思ったんです。
私は、雨の日になると髪の毛が広がっちゃうし、ぱさぱさになるし、それが原因で外に出るのも億劫になるし…」
「ああ、成る程ね」
真砂は私のこんな説明で納得したようだ。
うんうん、と頷き、手を伸ばして私の髪を撫でた。
「…確かに、湿気が多すぎるみたいね。…でもあなたなら、魔法の道具とやらで何とか出来るんじゃない?」
「――……!」
私は真砂の言葉に、ぴくりと震えた。
真砂は気にせずに続けている。
「私の不肖の孫にも作ってくれたでしょう。あの子もそうだけれど、私も本当に感謝してるのよ。
私の魔法薬は内服薬専門だから、ああいう物は作れなくって。…どうしたの?」
「…内服薬専門、なんですか…?」
私は思わず目を丸くして、じっと真砂を見つめていた。
きっとこのときの私の瞳は、きらきらと輝いていたのだろう。
「…る、ルーリィさん?」
「あのっ!お願いがあるんですけど!」
私はそう叫ぶように言って、がばっと真砂の細い手を掴んだ。
真砂は少し慄くように私を見つめている。
「私っ。魔法薬の調合がとてもとても下手で…!未だにうまく作れないの。
でも雨のために広がるこの猫っ毛をどうにかしたくって。真砂さん、お願いっ!」
「は、はい?」
私はずいっと顔を近づけて、真剣な表情で言った。
「…魔法薬の造り方、教えてください」
「……え?」
「…私は人魚の魔女なのよ。だから水に関することならお手の物だし、操ることも出来るわ。
でも教えるとなるとまた別よ。あなたとは流派が違うし、それにあなたにもお師匠がいるでしょう?」
「いいんですっ。どうせまともなこと教えてくれないんですから」
私はふん、と鼻息を荒くして答えた。そんな私を真砂は困ったような顔で眺めている。
…そうだ。元はといえば婆さまがちゃんと教えてくれないから悪いのだ。
何事も才能だ、とか言っちゃって、あの人自身魔法薬は専門じゃないからなのに。
「…あなたのお師匠が教えないことを、私が教えていいと思う?
それにあなたも魔女なら分かると思うけど」
真砂は一呼吸置いて言った。
「魔女は気安く”願い事”を叶えるものじゃないのよ。それなりの代償も必要になるわ。
…勿論、それを分かった上で言ってるのよね?」
「………う。」
私は思わず唸った。確かに、真砂の言うとおりだ。
長いこと願いを叶える側にいたから、忘れていた。
願いを叶えるには、代償が必要。そして、他人には窺い知ることは出来ないけれど、少なくとも本人にとって、
本当に願うことでなければいけない。それが魔女の決まり。
…私の言ったことは、本当に”願うこと”だったのだろうか?
「………まあ」
真砂は見かねたように、うな垂れた私の頭をぽんぽん、と撫でて言った。
「その薬を作ってあげることも、造り方を親切丁寧に教えることもしないけど。
ヒントだけなら、教えてあげられるわ」
「……え?」
私は真砂の言葉に、思わず顔を上げた。
私の目に飛び込んできたのは、真砂の顔に浮かんでいるにっこりとした笑顔。
「ヒントその1。私は水の魔女。主に操るのは水の眷族よ。
その2。人魚の鱗は保湿性があって、余計な水分を弾いてくれるわ。
その3。―――不肖の孫が先日あなたに渡したものは?」
「………あ。」
私は思わず、ぽかんと口を開けていた。
そうだ。何かに使おうと思って保存したまま、すっかり忘れていた。
この前この真砂の孫という少女に貰ったのは、正真正銘人魚の鱗。
…何せ、あの少女自身の鱗なのだから。
「そうかっ。あの鱗、使えばいいんだ!」
私はそう叫んで、がたんと椅子から立ち上がっていた。
そんな私を、真砂はにこにこと笑いながら見上げている。
その笑みはどことなく悪戯っぽいものだったが。
「そう。私が言うのも何だけど、人魚の鱗は最高級の材料よ。
大事に使って頂戴ね?…あれを使うなら、簡単なミスはしないと思うけど」
「はいっ。勿論、大切に使います。よぅし、これで今年は梅雨の時期も乗り越えそう!
ありがとう、真砂さん。私、早速試して見ますね!」
そう言って二階に上がろうとした私の腕を、真砂の手ががしっと掴んだ。
華奢な手なのに、どこからそんな力が出てくるんだろうと思うほどに、強く。
「…真砂さん?」
振り返った私の眼の中には、先程と同じ真砂の笑顔。
だが今は、その笑顔が少し違うように見えて。
…そう、例えるなら、どこかの研究者のような――…。
「折角だから、少し見学していこうかしら。それぐらいならいいわよね?ね?」
「……わ、私は構いませんけど…!」
教えるのはダメ、じゃなかったのだろうか?
そんな疑問が浮かんだが、敢えて口に出さないことにした。
多分、この真砂と言う人は―…魔法薬がすきなのだ、きっと。それだけではなく、作る過程までも。
「…あ、じゃあ。間違ってたら教えてくださいね?」
「それはダメ。」
私の哀願を一蹴し、真砂は楽しそうにうきうきと、私の腕を取ったまま二階へと足を運ぶのだった。
――――訂正。魔女に必要なものは優美さと、全てを見透かす瞳と、それからそれから。
変わり者であること。…きっとそうなのだ。
End.
●○● 登場人物(この物語に登場した人物の一覧)
――――――――――――――――――――――――――――――――
【整理番号|PC名|性別|年齢|職業】
【5199|竜宮・真砂|女性|750歳|魔女】
●○● ライター通信
――――――――――――――――――――――――――――――――
この度は書かせて頂いて有り難う御座いました。WRの瀬戸太一です。
そして、遅れてしまい申し訳ありませんでした;
今回はほぼお任せということで、大分試行錯誤しながら書かせて頂きました。
このノベルが真砂さんの第一作目ということで、
そういった面でPLさんのイメージと違っていたら申し訳ありません;
PLさん的真砂さんイメージに近づいていたなら、大変嬉しく思います^^
そして、先日の孫人魚さんのことも少々ネタにさせて頂きました。
楽しんで頂けると幸いです。
それでは、またどこかでお会いできることを祈って。
|