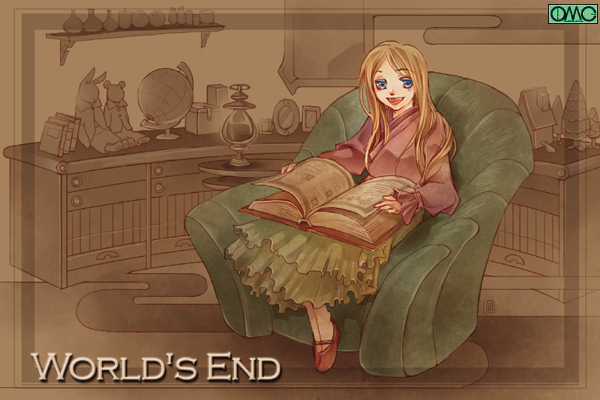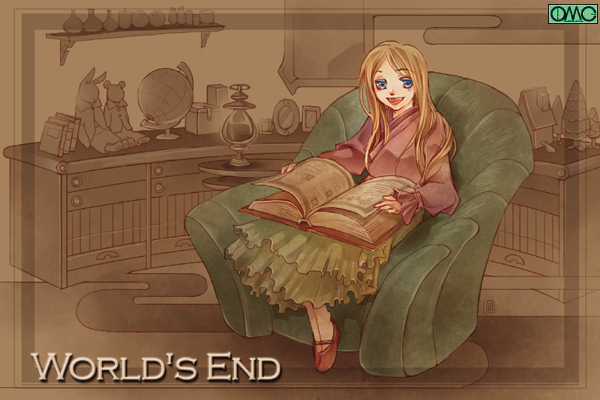■ワンダフル・ライフ〜特別じゃない一日■
瀬戸太一 |
|
【3885】【アレシア・カーツウェル】【主婦】 |
お日様は機嫌が良いし、風向きは上々。
こんな日は、何か良いことが起きそうな気がするの。
ねえ、あなたもそう思わない?
|
ワンダフル・ライフ〜MOTHER/母の場合。
「ふぅ、暑い暑い」
「母さん…なんかね、体がじめっとするの」
私が団扇を片手にぱたぱたとやっている隣で、リネアが泣きそうな顔をしていた。
既に暦の上では梅雨に入り、一応外は晴れているものの、その空気は水分を含んで重苦しい。
このジャングルの雨季にも似た湿度の高い空気は、それに慣れていない私にとって、
体中の気という気を吸い取られていくような気分がする。
そしてリネアはというと、この子は元々の体が木でできているものだから、水分を尚更吸い取りやすいのだろう。
…カビやキノコなんかが生えないことを祈るばかりだ。
「リネア、もー少し我慢したら、夏が来るわよ」
「夏って何?これより酷いの?私、体が重いのもうイヤ!」
リネアはそう言って、ぷぅと頬を膨らませた。
私は苦笑を浮かべ、団扇で彼女を仰いでやる。
…本当、リネアじゃないけどこの湿気は些か厳しい。
やはり何の対策もせず、日本の夏を乗り切ろう何て、土台ムリがあったのかしら。
私が早くも弱音を吐いていたとき、ふいに玄関のほうでドアベルが鳴る音がした。
私は団扇を仰ぐ手を止めてそちらのほうに顔を向けるが、
私なんかよりも早く動いたのは、先程まで散々愚痴を溢していたリネアだった。
(…銀埜の教育の賜物かしら)
客と見ると、何をしていても中断して駆けつけていた私の使い魔のことを思い出し、私はくすっと笑った。
その使い魔自身は今は不在なのだけれど、リネアなりに彼の役割を果たそうと頑張っているらしい。
「母さん、母さん!アレシア…さんが来たよ!」
「アレシア?」
私は団扇をカウンターの上に置き、椅子から立ち上がった。
リネアに手を引かれ、困ったような、そして何処かくすぐったいような笑顔を浮かべて此方にやってくる女性を見る。
豊かな金髪に吸い込まれそうな青い瞳。
一児の母なのだけれど、それを感じさせない若々しい外見。
もう随分と会っていないような気もするし、ついこの間顔をあわせたばかりのような気にもさせてくれる、
不思議な雰囲気を持つ私の友人。
私はそんな彼女を、満面の笑みを浮かべて出迎えた。
「いらっしゃい、アレシア!お久しぶり…なのかしら?」
「ええ、試験以来だから…暫らくぶりね。今日は少し用事があって、あの子も…あら、ローナ?」
アレシアはそう呟くように言い、自分の隣と背中のあたり、そして背後と順に視線を巡らせた。
私もアレシアの肩のあたりから、背を伸ばして背後のほうを伺ってみる。
すると。
「母さん、母さん」
何時の間に私の隣に居たのか、リネアがくいくい、と私のスカートを引っ張っていた。
「どうしたの?」
「あのね…女の子がいるよ?私と同じくらいの」
「女の子?」
はて。 私は顎に手をやり、首を傾げた。
リネアと同年代の少女、というと、私が思い浮かぶのは彼女ぐらいなもので―…。
そういえば、アレシアはさっき何て呼んでたっけ?
「Hi!After a long timeね、ルーリィ!」
ピッとまっすぐに片手をあげて、弾けんばかりの笑顔を向けている少女が、アレシアの隣に立っていた。
きっとアレシアと共に店に入ってきたのだけども、
そのあと店内を見て回ってでもしていて気付かなかったのだろう。
それはアレシアの一人娘、ローナだった。
いつか見たふわふわのくせっ毛は母親と同じ金色に輝き、ローナの笑顔を引き立てている。
その髪は男の子のようにとても短いけれど、そのうちアレシアのように伸ばしたりするのだろうか。
私はそんなことを考えながら身を屈め、ローナに笑いかけた。
「いらっしゃいませ、ローナちゃん。今日はお母さんと一緒にお買い物かしら?」
「Yes!ママが来るから、一緒に来てみたのよ。ねえ、リックは?wingは!?」
「リックは二階にいるわよ。あとで呼んでくるわね」
…やはりこの子の中では、リック=羽根なのだろうか。
少し不憫な気もするし、同時に微笑ましいものも感じる私だった。
そして、私の隣にいるリネアのことを思い出す。
リネアは私のスカートを掴みながら、何かを訴えるように私を見上げていた。
…そういえば、リネアは年上のお客様とはよく話す機会もあるし、身の回りにいるのも大人ばかりだったから、
あまり同年代の友達を作るきっかけがなかったんだっけ。
良く考えてみれば、あの学校のおままごとをしたときぐらいだわ。
…リネアが照れるのもムリないわね。
「リネア、リネア」
私はリネアの肩をぽん、と叩き、カウンターの横のほうに出るよう、背中を押してみる。
リネアはカウンターの後ろにいるので、あまりアレシアたちの様子が分からないのだ。
「恥ずかしがってちゃお友達にはなれないわよ?まず挨拶からやってみなさいな」
「…う、うん」
リネアは顔を強張らせながらこくん、と頷き、てこてことカウンターの前に出た。
そんなリネアに気付き、アレシアが笑顔を送ってくれる。
「リネア、そんなところにいたの?お久しぶり、元気だったかしら」
「アレシア…さん、私は元気だよ。今日は来てくれて有り難う!」
「いえいえ、どう致しまして。…あら、私は姉さんじゃないのね」
リネアの口癖―…兄さん、姉さんと敬称をつけて呼んでしまう―…を知っているアレシアは、くすくすと笑いながら言った。
リネアは顔を真っ赤にして首を振り、
「だって、アレシアさんは母さんでっ…姉さんじゃないし、でもおばさん…も失礼だし。
だからアレシアさんなの。…ダメだった?」
「ふふ、おばさんでも良いのよ。実際、年齢的にはそう呼ばれてもおかしくないもの。
…でも嬉しいわ、ありがとう」
アレシアはころころと転がるような笑みを見せたあと、傍らに居た自分の娘の背中を押した。
「リネア、私の娘のローナよ。…よろしくしてね」
背中を押されたローナは一瞬母親の顔を見上げ、そしてニコッと笑ってリネアのほうに視線を向けた。
リネアはというと、素直に笑顔も浮かべられず、どぎまぎとしたまま。
…これは我が事のように…ううん、それ以上に緊張するわね。
私が手に汗を握っていることを知ってか知らずか、ローナは笑顔で語りかけてくれた。
「Hi、My name is Lorna Kurzweil!Youの名前は?」
「あ…私、リネアって云うの。…ローナちゃん?」
「Yeah!リネアね、ヨロシクっ!」
しゅばっと音が聞こえそうな素早さで、手を前に出すローナ。
リネアはそれを恐る恐る握り返し、にこ、と笑みを浮かべた。
私はその様子を眺めながら、ふと視線を感じて顔を前に上げると、アレシアと目が合った。
そしてどちらともなく微笑んで、ふ、と溜息を漏らす。
――…あとで聞いた話だが、このときアレシアのほうも内心胸がはらはらしていたらしい。
母親というものは、なんともかんとも―…心配性に成らざるを得ないものなのだ。
「ママ!リネアが部屋にinviteしてくれるんだって!」
「まあ…招待して頂けるの?ご迷惑じゃないかしら」
何時の間に意気投合したのか、二人の少女は手を取り合って、階段へと向かうカーテンをめくろうとしていた。
そんな二人に、アレシアは心配そうな顔を向ける。
「大丈夫だよ、アレシアさん。変な物とか置いてないから、母さんの部屋と違って」
「…リネア、私の部屋も大して変なものは置いてないわよ!」
ほんとにもう、と私は憤慨して手を組むが、あはは、と笑い飛ばされる。
…まあ、仕方のないことだけども。
「リネア、それにルーリィ。そんなことを心配してるんじゃなくって…ふふ、まあ良いわね。
ローナ、勝手に弄っちゃ駄目よ。あとシュークリームを持ってきたから、あとで降りてらっしゃいね」
「Oh!やったあ、ママのシュークリームはvery、very、おいしいのよ!」
「本当?ありがとう、アレシアさん!」
二人はそんなことを言い合って、はしゃぎながら二階へと上がっていった。
この店では珍しい、そんな幼い少女たちの明るい声を聞きながら、私はアレシアに笑顔を向けた。
「二人が仲良くなって良かったわ。ホッとしちゃった」
「ええ、そうね。…私も一安心だわ」
そして私は、アレシアが先程から片手に抱えている大き目の長方形の形をした包みに目をやった。
…あれかしら?
「ああ。…お察しの通り、シュークリームよ。割と沢山作ってきたから、あとでお茶にしましょうね」
「あ…あはは!ごめんなさい、アレシアが作るんだからきっと美味しいんだろうなって…あははは!」
私は笑って誤魔化しながら、内心穴があったら入りたい気分だった。
―…食い意地張りすぎ、私。
■□■
「期せずして、やりやすくなってしまったわね」
「え?」
私はお茶の用意を整えながら、いそいそとアレシアの椅子を出していた。
手持ち無沙汰に店の中を眺めていたアレシアが呟いた言葉に、私は首を傾げる。
…何て云ったんだろう?よく聞き取れなかった。
「ごめんなさい、何て?」
「あ…いえ、独り言なの。こっちの話」
アレシアはにこ、と笑って首を振った。
私はふぅん、と訝しく思いながらも、今しがた出してきた古いアンティーク調の椅子を彼女に薦めた。
「まあ、どうぞどうぞ。立ち話もなんだし…ね?」
「ええ、ありがとう」
冬は暖かな火が灯っている暖炉には、今は何も入っていない。
その元暖炉の前に設えたテーブルに私たちは向かい合わせに座った。
「お茶菓子はあとで皆で頂くとして…ささ、紅茶でもどうぞ?
私が淹れたから、あんまり美味しくないかもしれないけど」
私は苦笑しながら、彼女の前のグラスを薦めた。
ホットの紅茶も好きだけど、こんな蒸し暑い日にはやはりアイスだろう。
アレシアは、あら、と首を傾げてグラスを傾けたあと、笑って云った。
「そんなことないわ。…美味しいわよ、ルーリィ」
「え、そう?あはは…有り難う」
「そういえば、今日はあなたが…ということは、彼はお留守なのかしら?あの背の高い…銀埜さん」
アレシアがふと思い出したように云った。
私はうんうん、と頷き、
「そうなの。ちょっと買い物に出しててね…外は暑いから、どこかで涼んでくるって云ってたわ。
多分夕方にならないと戻ってこないんじゃないかしら」
「そう…あの人にも言っておきたかったけれど、仕方ないわね」
アレシアは何処か憂いを秘めた表情で、ふ、と笑った。
私はその表情を見て、何か不吉なものを感じた。
…銀埜にも言っておきたいことがあった?…何だろう。
それともあの子が何か粗相でも犯したのかしら。
「…アレシア、正直に言ってね」
「…どうしたの?」
私は切羽詰まった顔で、ずずいと彼女に身体を近づけた。
アレシアは目を丸くし、きょとんとしながらも私に合わせて少し身体を引く。
「…銀埜が何かやったの?あの子一見礼儀正しいけど、実はそうじゃないのよね。
慇懃無礼って云うのかしら、あれは。時々すんごい毒吐くことがあって…アレシア?」
私は滔々と語っていたが、ふとアレシアの様子を見てみると、彼女は少し顔を伏せ、肩を震わせていた。
…もしかして…アレシア、泣いてる?
「ねえ、どうしたの?やっぱり銀埜が何かしたの?ごめんなさい、私…!」
「ち、ちがうわ…そうじゃないの。ルーリィ、その早とちり…ふふっ、全然治ってないのね」
「…え?」
――…早とちり?
私はぴた、と固まった。
そんな私に、アレシアはくすくす、と笑いながら云う。
「そんなのじゃないの。勿論、銀埜さんに何かされた覚えはないわ。あの人はとても優しい紳士でしょう?
そうじゃなくて…謝りたいことがあったから」
「へ…?う、うん。謝る…?」
私は呆然、としながら笑顔のアレシアを見つめていた。
謝るという内容がどんなことかは知らないけれど…とりあえず言えることは。
「…私の、勘違い…?」
「ふふ、そうみたいね。ルーリィったら、おっちょこちょいなんだから」
…そうして私は、また顔を真っ赤にする羽目になった。
「そ、それはそうとして…!それでどうしたの、今日は?」
私はドン、とテーブルを軽く叩いて仕切り直し、アレシアのほうを見た。
アレシアは一瞬固まるが、すぐにええ、と頷く。
「…そう。少し前…最終試験のことになるけれど」
「最終試験?ああ…私の?」
「ええ、そうよ」
アレシアの言葉に、私は自分の魔女検定試験のことを思い出す。
アレシアには、一次から最終まで手伝ってもらった。
最終試験は、確か…魔力を吸い取られて意識まで離れていたけれど、
アレシアがこちら側に連れ戻してくれたんだっけ。
…そういえば、彼女はどうやって連れ戻したんだろう?
あのときのことは私は朦朧としていて、実をいうと良く覚えていないのだ。
「…ごめんなさい、あのときは私も殆ど意識がなくて…私、何か変なことでもやった?」
「いいえ、そういう意味じゃないのよ」
アレシアは私の言葉に、ゆっくりと首を振る。
「…覚えてないのね?」
彼女の言いたいことは、やはりあの試験真っ最中のことだろう。
そうなると、私は首を縦に振らざるを得なくなる。
私は申し訳なさそうに頷いた。
「…ごめんなさい。アレシアが助けてくれた…っていうのは覚えてるんだけども」
「いえ、良いのよ。…そう、私が、というのは意識にあるのね。じゃあ、其のうち思い出すかもしれない…」
「アレシア?」
私はブツブツと呟くように云うアレシアに首を傾げた。
アレシアは私のほうを見て、何処となく強い意思を秘めた瞳を向けた。
それは初めて会ったときに感じた悪寒なんてものはなく、
吹っ切れたような…そんな彼女らしい包み込むような強さが秘められた瞳。
…なら、大丈夫。彼女が何を言おうとも、危惧することは何もないわ。
「あのときも言ったけれど…もう一度云うわね」
「うん?」
私は首を傾けて、彼女の言葉の続きを促した。
アレシアは一呼吸置いて言った。
「ごめんなさい…今まで隠していて。私はね、魔女なの。
あなたと同じ…だけど流派は違うけれど。でも、魔女の血は持ってる」
「―………」
私は目を見開いて、アレシアを見つめていた。
彼女が…魔女。でも隠していたということは、大っぴらに知られたくない理由があるのだろう。
それに、彼女は普通の人間としての生活を送っている。
…ならば、それこそが『隠しておきたい理由』なのだろうか。
「アレシア…ありがとう」
「……」
彼女はほんの少しだけ目を大きくして、私を見た。
私はふ、と笑って続ける。
「ずっと何もしなければバレないのに…それでも私を助けてくれた。だから、有り難う」
「…だって、貴女は大切な友人だもの。私の力で助けられるものならば、と思ったわ。
それに、隠していたのはこっちの理由だもの。だから―…」
「でも、隠していたのに助けてくれたでしょう?私はそれがとても嬉しいの。
それに、誰でも隠し事ぐらいあるわよ。それを黙っていたから怒るぐらい―…」
私は心が狭く見える?
そんな私の言葉に、アレシアはふっ、と笑顔を見せた。
…うん、彼女に思い詰めたような顔は似合わない。やっぱり、笑顔でいなきゃ。
「見えないわね、確かに」
「でしょう?」
私はそう言って、肩をすくめて見せた。
「それはそうだけども―…私なりのけじめとして、改めて謝っておきたかったの。
…だから、御免なさい」
アレシアは改めて居住まいを直し、軽く頭を下げた。
それを遠慮するのは、むしろ失礼だろう。なので私も頭を下げて云う。
「いえいえ、どう致しまして―…っていうのは変かしら?」
私が頭を上げて首を傾げると、アレシアはふふ、と笑った。
―…うん、日本語って難しいわね。でも、きっと気持ちは伝わったわ。
そして、そういえば、と私はふと思い出した。
「…ローナちゃんは…知ってるの?ううん、知らないわね。そんなこと言ってなかったもの」
「―…ローナは…」
私の言葉に、アレシアはぴたり、と身体を強張らせる。
「ローナちゃんは、魔女だとか魔法だとか―…そういうものが大好きなの、知ってるんでしょう?」
「ええ…あの子は憧れを持ってるみたいね。ルーリィにもねだったんでしょう?」
「あ…ううん、私は大したこと出来なかったし!
じゃなくて、ローナちゃんは、お母さんが―…そうだったら、とても喜ぶと思うんだけど」
あの明るく強い少女なら、きっと受け入れられるだろう。
私はそんな意味を込めて尋ねるが、アレシアは口元に笑みを浮かべたまま、ゆっくりと首を振った。
「…いいえ、まだその時期じゃないわ。いつかは話さなければいけないのかもしれないけど―…
それは自分自身でやりたいの。娘にも、夫にも」
「―…そう。そうよね」
私はうん、と頷いて笑顔を見せる。
「大丈夫、誰にも言わないから。アンクルとコーシア、そしてカルカツィアに誓うわ」
私はそう言って、人差し指と小指を立てて手を掲げた。
魔女の村に伝わる、誓いのポーズ。
「アンクル…何ですって?」
「ええとね、私たちの村の創始者。偉大な三人の魔女が、私たちの村を作ったの。
だから誓いの言葉や呪文には、彼女たちの名前が含まれているし―…そうね、人間たちが神に誓うのと同じようなものかしら」
「そういうのもあるの、ふぅん…初めて聞いたわ」
アレシアは感心したように頷き、
「そう。…あの子をルーリィに弟子入りさせるのも、悪くないわね」
「え?…本気?」
アレシアがぼそっと呟いた言葉に、私は耳を疑った。
弟子って…それは嬉しいけども。でも―…。
「アレシアの娘じゃ、すぐに追い越されそうだわ。何せ天然物だもん」
「あら、そんなことないわよ。…そのときまでに、ルーリィがもっと成長していたら良い話じゃない?」
アレシアはくすっ、と悪戯っぽく笑った。私はあはは、と苦笑交じりに返しながら、内心とても慄いていた。
…こりゃあ、暑い暑いってバテてる場合じゃないわ。
…そう、暑いっていえば。
「あのね、話は変わるけど、日本の夏ってもっと大変?クーラーって要るかしら」
「え?クーラー?」
アレシアはきょとん、として首を傾げた。
私は身振り手振りを交えて必死に語りながら、穏やかな時間が過ぎていくのを感じていた。
■□■
「わぁい、シュークリームシュークリーム!」
鼻歌を歌うように足取り軽く、娘たちが降りてくる。
「ローナ、リネアのお部屋はどうだった?」
カチャカチャ、とお茶の準備をしながら、アレシアが尋ねた。
「うん!It is interesting!とーってもステキだったよ!ママの絵も描いたの。
あとで見せてあげるね!」
「そう、それは良かったわね」
それは、普段の彼女たち親子の生活を垣間見てるようで。
私はほんわかした気分になりながら、テーブルの上の箱を覗き込んでいるリックを呼びつけた。
何故かリネアたちと一緒に降りてきたリック。
今は人間の姿をしているから、きっと二人と一緒に遊んでいたんだろう。
私はリックにぼそぼそと囁くように尋ねた。
「…どうだった?あの子達は」
「別にフツー。ああ、ルーリィがあげたアレで楽しんでたぜ。
ほら、前に作ってやったじゃん?紙と色鉛筆のセットでさ、紙に書いた絵が動き出す奴。
あれ、ホントは立体的に動かそうと思ったんだけど失敗したんだよな。俺は知ってんだぜ」
けけけ、と意地悪く笑うリックに私は腹を立て、ぐい、と耳を引っ張ってやる。
「昔の失敗談を穿り返さないで頂戴。…それで、暴走したりしなかったでしょうね?」
「ててて、離せよちくしょー!」
リックが大げさに暴れるので、私は仕方なく手を離す。
私が手を離した途端、リックがバッと飛び退り、アレシアのほうに避難する。
…あいつ、彼女の傍にいると怒られないと思ってるのかしら。
「暴走なんてしやしねーよ。する程魔力込めちゃいねーじゃん!
暴走したのはガキたちのほう!俺は関係ねーもんねーってオバサン、あれあんたが作ったの?」
「ちょっ、リック!おばさんって、アンタ…!」
私はわたわたと慌てながら、口をぱくぱくさせた。
全く、この子は―…!
「…出来れば、名前で呼んでもらえると嬉しいわね、リックくん」
だがアレシアのほうは動じず、にっこりと笑って言った。
「私はアレシア・カーツウェル。リックくん、いつもローナと遊んでくれて有り難う」
「あーあーあー、オバサン…じゃねえ、あんたがアレシア?ふぅーん…そういえば一回会ったよな」
「…あら、そうだったかしら?」
アレシアはきょとん、と首を傾げるが、リックはにやりと笑い、
「そうなの。ほら、初めて店に来たとき、コウモリいたじゃん?」
「ああ…元気なのが一匹居たわね、そういえば」
「ママ!あれがリックなのよ!リックはBatなの!Wingもあるのよ」
リネアと一緒に皿を運ぶ手伝いをしながら、ローナが顔を輝かせて云う。
アレシアはまあ、と驚いたように目を丸くしてリックを見た。
「へへん、そーいうことでさっ。いっつもあのクソ魔女の腑抜けた面ばっか見てるもんだから、
あんたみたいな美人サンが入ってきてくれて助かったぜ。眼の保養、眼の保養…ってな」
「リック…あんた、い・い・加・減・に・し・な・さ・い・よ・ね・?」
「はっ」
リックは背後から立ち上る異様なオーラを察し、ダッシュで逃げようとするが、それを逃す私じゃない。
「さっきから聞いてりゃ勝手なことばっかり…。あんたのその口の悪さ、どうにかしなさい。
誰がクソ魔女ですって?」
「わー、わー!勘弁勘弁っ。ありゃあただの言葉のあや…っていうか、ルーリィこそリースに似てきたんじゃねーのか!?
口悪いぞ、お前もっ」
そんな騒々しい遣り合いを繰り広げている隣では、何とものんびりとした会話が広がっていた。
「…リネア、リースって?」
「母さんの幼馴染。イングランドからこの間、東京に来たんだって。
今は二階にいるけど…アレシアさん、会わないほうがいいかも…」
「What?リースは楽しいよっ。A lot lot 面白いよっ!」
「そうかなあ…多分そう言ってくれるの、ローナちゃんぐらいだと思うよ」
リネアははぁ、と溜息をつくが、アレシアは気にしていない様子で皿の枚数を確かめる。
「そう。…なら、1枚足りないわね。ローナ、出してきてくれる?」
「Yes,mam!了解ねっ」
ばたばた、とリビングに向かって駆けていくローナを見送り、リネアはアレシアを不安そうに見上げた。
「…多分呼ばなくてもいいと思うんだけど…」
「あら、折角いるんだもの。大勢のほうが楽しいし…それとも、リースさんはシュークリーム、嫌いかしら?」
「ううん、大好きだと思うよ。でも…」
うんうん、分かるわリネア。リースがアレシアに何か暴言吐くんじゃないかって心配なのよね。
私もそうだもの…。
私はリックの両耳を引っ張りながら、しみじみと頷いた。
そしてきっとすぐに、一階の騒々しい音に気がついて、眠れやしないとかぷりぷり怒りながら、リースが降りてくるんだろう。
その頃には、もう銀埜も帰っているかもしれない。
そうしたら、みんなでお茶が出来るわ。
美味しい美味しいアレシア特製のシュークリームと、銀埜が淹れたお茶を囲んで、皆で穏やかな時を過ごすの。
「…このメンバーだと、そうはならないかも」
「え?」
私の独り言を聞きつけたアレシアが、ふと首を傾げた。
「どうかした?ルーリィ」
「ううん、ちょっとね…。落ち着いたお茶じゃなくって、騒々しいお茶になりそうだなって…」
苦笑を浮かべた私を安心させるかのように、アレシアがふふ、と微笑んで言った。
「賑やかなお茶も良いものよ。それに―…」
―…楽しんで食べてもらえたほうが、お菓子もきっと嬉しいわ。
「…それもそうね」
私はぽん、と手を叩き、またいそいそとお茶の準備を始めるのだった。
友人たちとの楽しい―…否、少々騒々しい語らいのために。
End.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼ 登場人物 * この物語に登場した人物の一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【整理番号|PC名|性別|年齢|職業】
【3885|アレシア・カーツウェル|女性|35歳|主婦】
【1936|ローナ・カーツウェル|女性|10歳|小学生】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼ ライター通信
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アレシアさん、ローナさん、そしてPL様。
母子でご参加して頂き、誠に有り難う御座いました。
そして遅延、申し訳ありませんでした;
遅れた分、気に入ってもらえると大変嬉しく思いますが…;
今回は初めての母子同時参加ということで…
一緒にいる場面をもう少し描きたかった気持ちもありますが、
お話の流れ上、大部分を個別化して書かせて頂きました。
母verはルーリィ視点、娘verはリネア視点ということになっております。
片方のノベルで描写していない場面は、もう片方で書いておりますので、
あわせてご覧になって下さいな。
それでは、いつもうちの店の連中と遊んで下さって有り難う御座います。
またの機会がありましたら、どうぞまた遊んでやってくださいませ^^
|