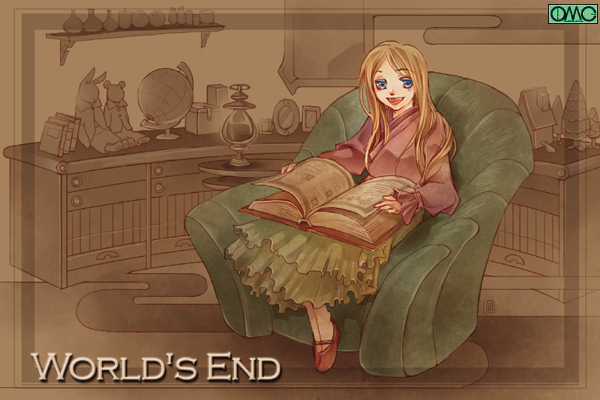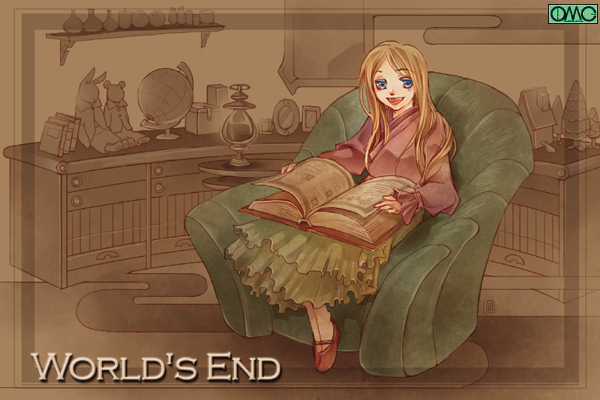■ワンダフル・ライフ〜特別じゃない一日■
瀬戸太一 |
|
【4958】【浅海・紅珠】【小学生/海の魔女見習】 |
お日様は機嫌が良いし、風向きは上々。
こんな日は、何か良いことが起きそうな気がするの。
ねえ、あなたもそう思わない?
|
ワンダフル・ライフ〜秋の匂いに誘われて。
「う〜ん、秋晴れっ!」
私は店の前でそう一人ごち、ううん、と大きく伸びをした。
空を見上げると、雲が疎らに浮かぶ真っ青な晴天。
そんな空の下に立っている私の傍ら、店の壁には竹箒が立てかけてある。
こんな良い日に閉じこもっているのも何だから、といそいそと店の前を掃除しに来たのだが。
「…こう良い天気だと、逆に掃除してるのが勿体無くなってくるわねえ…」
むしろ、遊びに行きたくなってしまう。
お弁当を広げて、どこかの公園でピクニック。もしくは、うちの大型犬を連れてゆっくりとお散歩。
紅葉にはまだ早いかしら、でも近所のお寺めぐりなんかをするのにも良い季節。
ああ、わくわくする。
でも一応掃除するって言って出てきたんだし、それにこの季節過ごしやすいのいいんだけど、
乾燥し易いせいか埃が舞いやすくなってしまっている。
だからやっぱり、今こうして箒を動かすのが正しいかもしれないんだけど。
私は竹箒を手に取り、少しだけ身を屈めて箒の手に乗せた手の甲に、自分の顎を乗せてみた。
「あーあ、退屈」
こーんないいお天気なのに。
リネアは自分の部屋で、銀埜に付き添われてお勉強。
リースはこれまた自分の部屋兼研究室で、なにやら新しい変化術の実験をしているらしい。
リックは、というと、普段の放浪癖を最大限に発揮して、
文字通り”羽を伸ばしに”何処か離れた場所へ飛んでいってしまった。
…ったく、昼間っから飛び回るコウモリだなんて、学者さんやテレビ屋さんに見つかったら、とっ捕まっちゃうんだから。
先ほどまでは秋晴れの下颯爽と箒を動かす自分の姿を、うきうきとしながら想像していたのに。
いざ始めるとなると、急にどこかに遊びに行きたくなるだなんて、私の思考も結構現金だ。
各々好き勝手やっているうちの子たちの代わりに、私の話し相手になってくれるような。
そんな人、現れてくれないかしら?
「……そうそう都合良く物事は起こらないものよねえ…」
自分で想像したあとに、ハァ、と溜息をつく私。
世界は自分を中心に回っているわけではない、と知ってるからこそ、期待をしたくなるというものなのだ。
「あーあ…」
誰もいない店の前で、またまたぼやこうとした私は、急に視界が真っ暗になったことに気がついた。
「へっ?!」
私は素っ頓狂な声をあげ、バッと顔を上げた。
だが視界は元に戻らない。
「え、え?誰っ!?」
私は慌てた声を上げながら、咄嗟に自分の目の辺りに触れてみた。
すると、暖かくって薄い皮膚のような感触を覚えた。
「……いきなり背後から目隠しするなんて、お行儀の悪い子は何処の誰かしら?」
私はそういいながら、口元に笑みを浮かべた。
いきなりの暗闇に驚いたけど、単に目隠しされていると分かれば焦ることはない。
私の背後から暫しクスクス、と子供のように高く、含み笑いを漏らす声が聞こえていたが、、
「ふっふっふ〜…だーれだっ?」
何故か得意気にそう言う、”何処かの誰かさん”の声がした。
私はその声を聞き、即座にあたりをつけた。
「……やんちゃな大和撫子候補さん?」
「ぶーっ。ちがいまーす」
私の問いに、背後からは楽しそうにバッテンをつける声が届いた。
なので私は、うーんうーん、と暫し唸るように考え込む素振りを見せたあと、
「じゃあ、朱色の綺麗な金魚さん?」
そう言ってみた。
だが背後からは、またもや同じ答えが返る。
「ぶぶーっ」
「うーん、うーん…じゃあじゃあ、若作りの和服美人さんの、お孫さん?」
「ぶぶぶーっ」
「ええとええと…じゃあ、無口な王子さまの、人魚姫さん!」
「!」
私のその問い呼応してか、柔らかい体温を感じさせてくれる手の平が、ふいに離れた。
突然のまばゆい世界に、私の目は暫ししばたく。
そして漸く慣れたあと、私はパッと後ろを振り向いた。
「…やっぱり、紅珠さん」
「えっへっへー」
私の背後に立っていた少女は、ぼりぼりと頭を掻きながらにや、と笑ってみせた。
私を目隠しするため背伸びでもしていたのか、片足ずつ宙でぶらつかせている。
…足、疲れちゃったのかしら。
「だーめだよ、ルーリィ。ちゃんとピタリと当てなきゃ」
「あらそう。残念、ピタリ賞は逃しちゃったようね」
参った参った、と私は笑顔を浮かべながら、先ほど視界が真っ暗になった際に、
思わず地面に落としてしまった竹箒を、しゃがみこんで拾った。
少女―…浅海紅珠は、そんな私をニヤニヤしながら眺めていたが、やがて含み笑いを漏らしながらこう言った。
「でもな、残念賞はあげるよ。惜しいところまでは当たったしな!」
「あら、それは光栄ね」
紅珠の言葉に、私は目を見開いてみせた。
当の紅珠は、そんな私の目の前で、人差し指を立てて、ピッと自分を指差して見せた。
「じゃーん、賞品は俺でっす。話し相手。欲しかったんだろ?」
「…!」
私は今度こそ、”本当に”目を見開いた。
そして暫し目を瞬いたあと、にっこりと笑みを浮かべて見せる。
「不思議、残念賞なのにちっとも残念って思わないわ。…改めていらっしゃい、紅珠さん」
「えへへ、いらっしゃいましたー」
或る秋晴れの日の、私と紅珠の出会いは、こんな形で始まった。
「そうそう、あの金魚鉢ありがとなっ」
店内を物珍しそうに巡っていた紅珠は、思い出したようにそう言って振り返った。
ホットの紅茶を出すか、それともフレッシュジュースを出すかで悩んでいた私は、
その言葉にふと、と顔を上げた。
「金魚鉢。…ああ、大きな金魚さん用のね」
「うん!あいつが持って帰ってきたときがびっくりしたけど、住んでみりゃなかなか居心地良くってさ。
水辺と陸地を作って、泳ぎ疲れたら陸地で休めるようにしたんだー。陸地には人形用のビニールチェア置いて、
そんで水の中にはキラキラしたビー玉とかサンゴの欠片とか置いてさっ。えへへー、自分の城って感じ」
紅珠は店の棚に置いてあるものをいじりながら、ニコニコと笑顔を浮かべてそう話した。
その顔は、彼女が自分の言葉の中に含んだビー玉のように、きらきらと輝いている。
金魚鉢、というのは、あるお客の手を介して彼女に贈られた、私特製の金魚鉢のこと。
中は異次元になっていて、金魚鉢の口を通すとどんなものでも小さくなってしまうもの。
私が睨んだとおり、彼女はその鉢を自分の住処として使っているらしい。
その言葉とその笑顔を見ているだけで、彼女があれを気に入ってくれたのだということが分かる。
なので私も彼女に釣られるように笑顔を浮かべ、
「そう。もう立派な金魚鉢ね。…ううん、この場合は人魚姫鉢って云うべきかしら?
何にせよ、気に入ってくれたなら私も嬉しいわ」
こちらこそありがとう。
そう言って私が笑顔を向けると、紅珠は照れたように自分の頭をぽりぽりと掻いた。
そんな彼女を見つめながら、私はふと、意地悪心を起こしてみた。
ああ、これが私のいけない癖なのよ。でも…仕方ないじゃない。ね?
「そういえば、紅珠さん」
「んー?」
棚に飾ってあった小さい人形を掲げ、それを不思議そうに眺めながら、紅珠が相槌を打つ。
「相方さんとは、仲良くやってる?」
にっこり。
私の笑みに反して、紅珠はその言葉を聞いた瞬間、ぎちり、と身体が固まったようだ。
私は予想通りのリアクションが返って来ることを期待して、やはり笑みを浮かべながら畳み掛けるように尋ねた。
「”でかすぎる金魚”に手を焼いていたようだけど。当の金魚さんは、どうなのかしら。
王子様のこと、困らせてない?だめよー、時にはこう、しおらしく女らしく…」
「わー!わー!わー!」
私の言葉を遮るように、紅珠は手をぶんぶん振りながら私のところに駆けてきた。
その顔は真っ赤。
私はその様子を見て、内心くすりと笑ってしまったが、ふと彼女の手の中にあるものを見て眉を顰めた。
…紅珠はいまだに、人形を握り締めながら手をぶんぶんと振っている。
大丈夫かしら…。
だがそんな私の懸念とは裏腹に、紅珠の挙動不審ぶりはエスカレートするばかりで。
「べ、別に困らせてるとかそういうことねーもん!俺だってちゃんと色々やってるよ!」
私はばたばたと手を振る紅珠を、微笑ましげに眺めながら、そう?と首を傾げてみた。
…ちなみに私の視線は彼女の手の中の人形へと注がれている。
「彼がいないことを良いことに、お風呂場で水を張って、悠々とお昼寝なんかしてない?
しかも彼が買いだめしてるミネラルウォーターなんか使っちゃってない?」
「わー!わー!」
私がわざとらしく首を傾げながら云うと、紅珠は真っ赤な顔をさらに赤くして、茹でダコのようになりながら両手をわたわたした。
「な、な、な、…何で知ってんのっ!!」
キッと私を睨み上げる紅珠。
私は素知らぬ顔で、
「あら、本当なの?単に、こんなことしてないかなーと思って言ってみたんだけど」
そしてまた、にっこり。
紅珠は私のそんな笑みを受けて、ぷしゅーっと頭から湯気が吹き出した…ように見えた。
「〜〜〜…っ!ずっこい!絶対…その、魔女の水晶球かなんかで、見てたんだろっ!
誘導尋問だ、人権侵害だーっ!」
そう叫ぶ紅珠を、私はどうどう、と暴れ馬をなだめるように肩を叩いた。
うーん…これほどまでの反応とは思わなかったわ。ちょっとからかいすぎたかしら。
「まあまあ。私は水晶球とかもってないし、そんなストーカーさんみたいな魔法、使えないわよ。
あとね、覚えたての言葉をとりあえず使ってみるのは良くないと思うわよ、うん」
「うーっ、うーっ!」
ぷしゅーっと頭から湯気を噴出しながら、なにやら唸る紅珠。
私は苦笑を浮かべ、そんな彼女に向かって手を合わせた。
「ごめんなさい、ちょっとからかいすぎたわ。だからね、そろそろ…落ち着いて?」
顔を真っ赤にしている紅珠の手の中で、何かがみし、と潰れる音がした。
その絶望的な音を聞いてしまった私は、もうあんまり人をからかうのは止そう、とそう思った。
そして数分後。
何とか無事に救出した人形を棚に飾りなおし、私はやっとこさ顔の色が元に戻った紅珠のところに行った。
そしてぽんぽん、と背中を叩く。
「あはは、ごめんなさいね。でも思ったより純情で吃驚したわ、金魚姫さん」
「…!だ、だからもういうなって…!」
紅珠はぜいぜい、と肩で息をしながら、拳を握り締めた。
私はこれ以上店のモノを壊されちゃたまらないので、大人しくギブアップしてみた。
両の手の平を見せて、降参、のボディランゲージを見せる。
「はい、分かりました。もう言いません。でも…」
「でも?」
じろ、と紅珠が私を睨むように見る。
これ以上何かいったら承知しねーぞ、という目だ。
なので私は、もう一言だけ、のつもりで言ってみた。
「次は、お二人でいらしてみてね。一緒に揃ってるとこ見てみたいわ」
「〜〜〜っ!」
あら、また赤くなっちゃった。
うーん…見かけによらずの純情姫には、彼の話題を出すこともいけないらしい。
まあ、そんな彼女も可愛らしいからいいんだけど。
そんなことを思っていた私を他所に、赤くなった頬を隠すように、ばたばたと紅珠は店の中を駆け抜けた。
どこに行くのやら、と彼女の背を追いかけると、店の入り口のほうに向かっている。
そして紅珠は店の入り口にでん、と置いてあったビニール袋を両手で持ち、
少々ふらつきながら私のところに戻ってくる。
「はー、はー…っ、まあそういうのはもういいじゃん!な!
これお土産。秋の遠足で芋掘り行ってきたから、おすそ分け!秋らしくていいだろ?」
そう行って、紅珠は両手に持ったビニール袋を、どん、とテーブルの上に置いた。
その口からは、確かに紫色の皮を被ったままのサツマイモが、いくつも顔を見せている。
オマケによくよくみてみると、まだ土がついたばかりなのもいくつかある。
私はそれを覗き込み、感嘆の声をあげた。
「すごい!これ、全部紅珠さんが掘ったの?」
私の言葉に、紅珠は得意気な顔を見せた。
「へっへっへー、俺芋掘り得意なんだ。まだまだいっぱいあって、俺んちだけじゃ食いきれないからさ!
秋の味覚ってやつ。普通にふかしても美味しいし、スイートポテトなんかもいいよ!
産地直産だから、うまいぜー」
そう言って得意げに胸を張る紅珠。
私は目をきらきらさせながら、ビニール袋の中から数本サツマイモを引っこ抜いてみた。
形はいびつだけどもその分、自然の豊かさが詰っているように見えた。
芽のようなくぼみからちょろっと生えたひげがまた、堀りたて、という気分を引き上げてくれる。
…折角こんなに持ってきてくれたんだもの。
ただ料理に使うだけじゃ勿体無いわ。…うん、そう。
「ねえ、紅珠さん」
「ん?」
私は芋をいじっていた紅珠に声をかけた。
紅珠は不思議そうな顔をして、私を見上げる。
そして私は、にこ、と微笑んで言ってみた。
「……お腹、空いてる?」
ぺこぺこ!との紅珠の言葉に、私は決行を決めた。
決めたとなったら、あとは行動するだけ。
どすんばたん、と煩く何かを動かす物音に、何事かと部屋に引っ込んでいたリネアと銀埜も降りてきた。
久しぶりの再会を交わすリネアと紅珠を他所に、私は銀埜を引き込んで手伝わせることに成功した。
何やら変な色が染み付いているカーペットを、二人して店のど真ん中に敷く。
テーブルや椅子、あと細々とした棚はもう既にカーテン裏のリビングへと引っ張り出していた。
あとはこのカーペットを敷いて、そして薪を数本持ってくるだけ。
薪は冬の暖炉用に倉庫に備蓄してあるから、問題なし。
この時点になって、漸く銀埜は眉を顰めて私に尋ねた。
「…ルーリィ、まさか…あなた…」
「ふふふ。秋といえばこれよ」
私は得意気な笑みを見せた。
そんな笑みを見て、銀埜は一片の不安を抱いたようだが、それは一瞬後に現実のものとなる。
「かーさんかーさん!焼き芋って何?今からするのっ?」
紅珠に聞いたのか、彼女の腰に抱きついていたリネアは、輝かせた顔を私に向けた。
紅珠は紅珠で、にまにまとした笑みを浮かべている。
「そーだぞー。家ん中で焼き芋できるなんて、ルーリィんとこぐらいだよなっ。
リネア、焼き芋ってすんげー美味いんだぞ。ほくほくで、あまあまでー」
「ほんと?わたし、焼き芋って食べたことないんだ。そんなにおいしいの?」
「もっちろーん。炎の中で、こうはぜる感じがもー…たまんねーの」
うっとり、とした表情を見せる紅珠。
だがそんな紅珠とは裏腹に、銀埜はげんなり、とした顔を見せていた。
「…ルーリィ…こんな物置で眠っていたようなカーペットを引きずり出して、何をするかと思えば…。
焼き芋なら、裏の庭ですればいいでしょう。わざわざこんな…後片付けが…」
はああ、という大きな溜息をつきながら、それでも敷く手伝いをするところは、
彼らしいといえばそうなのだが。
私は慰めるように苦笑を浮かべ、
「まあまあ。裏庭はまだ池が残ってるし、店の中ぐらいしかやる場所がないのよ」
「そーそー。裏の池は残しておいてもらわないとっ」
「紅珠ねーさんのためにね!ねーさんがひからびちゃったら、銀兄さんのせいなんだからね」
子供二人が加勢して、銀埜ももう殆ど諦めたのか、はぁ、と最後の溜息を付いた。
「まあ…端から私が反対してどうとなることでもないのですがね。
とりあえず貴女方、火事にだけは気をつけてくださいよ。後が厄介ですから」
「はぁーい!」
子供二人は、揃っていい笑顔を見せて大きな返事をした。
私はうんうん、と微笑ましげなそんな光景を眺めている。
だがふと、目の前から刺す様な視線を感じ、不思議に思い、顔を前に向けていた。
…まあ、予想通り、銀埜の冷たい視線が私に注がれていたわけで。
「……あなたが一番心配なのですよ。わかっておられます?」
「……はぁーい」
そして、用意は整った。
カーペットの上には数本の細い薪が組まれ、火がくべられるのを今か今かと待っている。
周辺にはテーブルも椅子も何もなく、広々とした空間が出来上がっていた。
「なーなー、ルーリィ。ノリで用意してみたけど…マジで大丈夫?」
私の傍らにいた紅珠が、ほんの微かに眉を曇らせ、足元のカーペットを指差した。
…そういえば、まだ詳しく説明してなかったっけ。
「大丈夫よ。あのね、このカーペットは特殊な魔方陣が編みこまれてるの。
この上で燃やす火は適度な大きさを保ったまま、決して大きくならず、それで決して他には燃え移らないの。
魔法薬をつくるときって、こんな特殊な火が必要だから、それ用に、ね。
云わば、持ち運び用簡易炎、かしら」
「…そんな聖なる火を焼き芋に使う魔女なんて、ルーリィぐらいですよ」
もう諦めている銀埜は、苦笑を浮かべながらマッチを持って戻ってきた。
そして、はい、と目を丸くしている紅珠にマッチを手渡す。
「これは極普通の市販のものですので、ご心配なく。
どうぞあなたが火をつけてやってください」
「いいの?」
「ええ、お客様だもの。ほら、リネアも待ってるし」
そう言って、私はカーペットの向かい側…から遠く離れたところでワクワクしているリネアを指差した。
一応あの子は木の人形がベースだから、火は苦手なのよね。
でも焼き芋は食べたいから、あんなところで待ってるってわけよ。
「ふーん…じゃ、紅珠いっきまーす!」
ピッと元気良く手を挙げ、紅珠はマッチを一本取り出した。
そしてシュッと箱の側面でこすると、直ぐに真っ赤な火が灯る。
「はい、これね」
私はそこらへんにあった紙のごみをくるくると丸めたものを、紅珠に手渡した。
紅珠はその紙の先端にマッチの火を移し、ぽい、と組まれた薪に放る。
そして残ったマッチも同じように放った後、ジッとカーペットの上を眺めていた。
「ほら、火が大きくなってきた」
私がそういったとおり、薪を飲み込み、火はどんどんと大きく燃え上がる。
だが紅珠の腰あたりまで大きくなると、カーペットに残る魔方陣が淡い光を放ち、
火はそれを受けてそれ以上大きくなることをしなかった。
「へえー…すっげえなあ。便利!」
「ふふ。こんなのでよければ、まだまだあるからそのうち見せてあげるわ」
「…主に物置に眠っていますけどね」
私は一言多い銀埜をじろ、と睨んでみた。
無論、銀埜はふいっと横を向き、素知らぬ振りをしている。
ああもう…ホントにこの子は。
「かーさん、ねーさんー。お芋、まだ?」
遠くのほうから、待ちくたびれた、というようなリネアの声がした。
それに呼応するように、傍らの紅珠もサツマイモが詰った袋を抱え、輝く笑顔を見せてくる。
「もーいいだろ。入れようぜ、芋っ」
「そうね。さー、どんどんいれちゃいましょ」
私がそう云うと、待ってました、というように紅珠は一本、二本とサツマイモを火の中にくべる。
私も負けじと放り込むが、とてもじゃないけれど一度にくべられる量でもない。
私がそう云うと、紅珠はにっと笑って、
「いいよいいよ、どうせ今全部焼いちゃっても、食べきれないし!
また何かに使ってみてよ」
「そうね…うん、じゃあ今は食べられるだけ食べちゃいましょうか」
うん、と元気良く頷く紅珠。
そんな彼女の笑顔を見ている私の横では、なにやらお経のようなブツブツとした声が響いていた。
それ即ち、「味噌汁…てんぷら…いや、田楽風も面白そうだ…」云々。
声の主は勿論銀埜。…どうやら今夜のメニューを考えているらしいけれど。
…田楽はちょっと違うと思うわ…。
「俺さー、火ってちょっと苦手だったんだよね」
いつの間にかしゃがみこんでいた紅珠は、まるで独り言のように漏らした。
私は思わず彼女のほうに首を向け、え?と返してみるが、
紅珠は燃える焚き木をジッと見つめながら、独白のように漏らす。
「やっぱさ、ほら…俺って水の眷属じゃん?
魚だから猫も苦手なんだけど…火は乾いちゃうし、それに燃えるの見てたら自分も燃えちゃいそうで。
だから、ちょっと苦手だったんだよ」
ぼうっと燃える火を眺めている紅珠の瞳には、きっと揺らめく炎が映っているんだろう。
私は紅珠を真似て、床にしゃがみこんでみた。
そして彼女の横顔を眺めながら、静かな声で云う。
「…この炎はどう?」
すると紅珠はニッと笑みを浮かべ、今までこらえていた笑みを噴出すように、明るい声で言った。
「ぜーんぜん!なんでだろ、魔法の火って知ってるからかな?
こんなに落ち着いて火を眺めていられるの、俺も不思議なんだ」
「…そう」
いくら魔法の火といっても、それを信じないと恐怖は拭えない。
紅珠は、私の魔法を―…ひいては私自身を、信じてくれているのだろう、きっと。
それは―…私にとって、この上なく幸せなことだ。
「…ありがとう」
「へ?」
私の漏らした一言を聞き取れなかったのか、紅珠は首を傾げて私のほうを見た。
だけど私はそれにはこたえず、よっこいしょ、と立ち上がって膝を支えた。
「さ、そろそろ焼ける頃じゃない?んー、香ばしい匂い!」
「なあ、今なんつったの?なー」
「ふふ、ヒミツー」
口を尖らせている紅珠に、私はそう言って、笑みを見せた。
言わないほうが華ってこともある。
それに―…私はほんの少し、先ほど顔を真っ赤にしていた紅珠のような気持ちだったので。
だから、やっぱり言わないでおこう、とそう思ったのだ。
紅珠の掘ってきた”産地直産”のお芋を、聖なる魔女の火でくべて。
そうやって出来上がった焼き芋は、美味しくないはずがなかった。
少し欲張って頬張り過ぎた紅珠が、お芋を喉に詰らせて少し危険な状態に陥ってしまったこととか―…
そういうことは、うん。私の胸の中に、そっと閉まっておくことにした。
また何かのときに、この金魚姫をからかうネタができたなあ、と思いつつ。
end.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼ 登場人物 * この物語に登場した人物の一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【整理番号|PC名|性別|年齢|職業】
【4958|浅海・紅珠|女性|12歳|小学生/海の魔女見習】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼ ライター通信
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いつもお世話になっております、いらして下さってありがとうございました!
ほのぼの雰囲気で、とのことでしたので、
持ってきてくださったお芋を使って焼き芋なんかをやってみました^^
きっと美味しいんだろうなあ、と石焼き芋の声を聞きながら思ってみたり。
秋の味覚、ありがとうございました。そしてご馳走様でした。(笑
個人的に楽しかった、わたわた場面。
気に入って頂けたかなあ、と思いつつ、大変可愛らしい紅珠さんを描くことができて、
私自身とても楽しかったです!純粋な面をみることもできましたし^^
また見る機会ができたらなあ、とかこっそり思っちゃってます。
それではまたお会い出来ることを祈って。
|